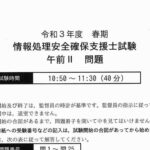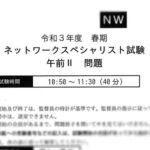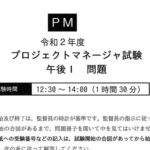3週間で仕上げる システムアーキテクト 試験 午後Ⅰ[午後1] の過去問を演習するとわかること【令和元年更新】
もくじ
Check-1. システムアーキテクトの 午後Ⅰの特徴 をチェック
情報処理技術者試験の高度系の記述式問題(午後Ⅰ、論述系以外の午後Ⅱ)は、試験区分によって、速く解くための “解答手順” が異なります。
そのため、いくら他の高度試験に合格しているからと言って、その “解答手順” が他の試験区分に通用しない可能性があるのです。過去の成功体験が、必ずしも次につながらないということですね。
では、システムアーキテクトの午後Ⅰ試験はどうかというと、次のような特徴があります。
- 階層化が 1 – 2 段階深い
- 図表が多い
- 解答は文中にある言葉を使うことが多い
- 販売管理の業務知識は少し難易度が上がる
システムアーキテクト 午後Ⅰの特徴
他の試験区分で言うとデータベーススペシャリスト試験と同じような感じですね。したがって、それぞれの特徴を加味した練習方法が必要になります。
Check-2. システムアーキテクト試験の午後Ⅰの特徴を意識した練習
その(1) 階層化が 1 – 2 段階深い
問題文を見てみると明らかなのですが、「(1)(2)(3)」や「 ① ② ③ 」が使われていることが多いですよね。
これはしっかりと体系化されていることも意味しています。あるいは箇条書きされていると言った方がわかりやすいかもしれません。
基本的にはそれが段落ごとに説明されているだけで、時系列に並んでいることは少なく、しかも設問を解くときには段落をまたいで、横断的に記述個所を探し出さなければならないという特徴をもっています。
箇条書きされている部分は、目的なく読んでしまうと瞬間的には記憶に残りにくい ので(暗記行為になります)、前から順番にただただ読み進めていくだけだと . . . 読んで忘れて、読んで忘れてを繰り返すことになってしまいます。
この結果、設問を解くときに、もう一度同じところを読み直さないといけなくなり、時間がかかってしまいます。
このため、午後Ⅰの問題文を読むにはコツがいります。
- 問題文のどこに何が書いているのかをチェック
- 細部に目を通すのは「設問に解答する」ときの方がいい
午後Ⅰの問題文を無駄に読まないコツ
こういった読み方になっているのかどうかをチェックしてみてください。
Check-3. その(2) 図表が多い
システムアーキテクト試験のもうひとつの特徴が、図表が多いという点です。
この特徴を上手く使えば、短時間で正確に解答できるようになる可能性があります。
- 問題文よりも先に、まずは図表を見ていろいろ考える
午後Ⅰ問題 の解答テクニック
一度試してみてください。特に、その図表を実際に使っている人には効果てきめんです。
そもそも図表とは、視覚に訴える目的で準備されているものなので、文章で伝わりにくい部分、全体像の提示など「文章よりも先に見る」ためのモノなんですね。
打ち合わせでも図表をベースに説明しますよね。提案などの場合でも「とりあえず、こちらが全体図です。ご確認ください」と言って、話を始めたり、質問を受けたりします。
その特徴を活かせば、下手に文章に惑わされなくなります。
しかも、図表の中に疑問点や違和感があれば、その説明をしている文章を “探す” という目的ができます。
箇条書きの文章は目的なく読むと暗記行為をしない限り「読んで忘れて」になりますが、目的があれば「サーチ」になるので “速読” で探せますし、何よりその目的が達成できた時に自然と記憶されます。
そういう意味でも、図表から読み解くアプローチも有効なのです。
Check-4. その(3) 解答は文中にある言葉を使うことが多い
これも当たり前といえば当たり前です。
「どの属性ですか?」とか、「どのテーブルを?」というのが問われることが多いので、その解答は問題文中で定義されているものを使うことが多いのです。
そういう意味では、それを「問題文中から探すのに時間がかかる」という課題を抱えているので、それに対応するだけの準備があれば万全でしょう。
- 業務、システム、テーブル(ファイル)、属性など、それぞれのレベルごとに、いくつ問題文中にあるのか?
- それは図表の中に整理されているのかいないのか?
- 問題文中にあるのなら、それはどことどこにあるのか?
午後Ⅰの解答の探し方
前述のとおり、特に設問で問われているキーワードが、段落横断的にあちこちに分散していることが多いので、例えば、こんな感じで問題文全体の構成を把握しておくことができれば、短時間で正確に解答できると思います。
受注処理に関しては、 7 つある処理のうちのひとつで、
以前の業務はここ(第 1 段落の ① など)、
旧システムは次の段落のここ、
要件はここ、
新システムはここ、
以上 4 つの箇所で説明されている。
ゆえに、この 4 か所だけを読めば、受注処理に関するこの設問には回答できる “
Check-5. その(4) 販売管理の業務知識は少し難易度が上がる
この点に関しては、ITストラテジスト試験の午後Ⅰのところで説明しているので、そちらを参考にしてみてください。
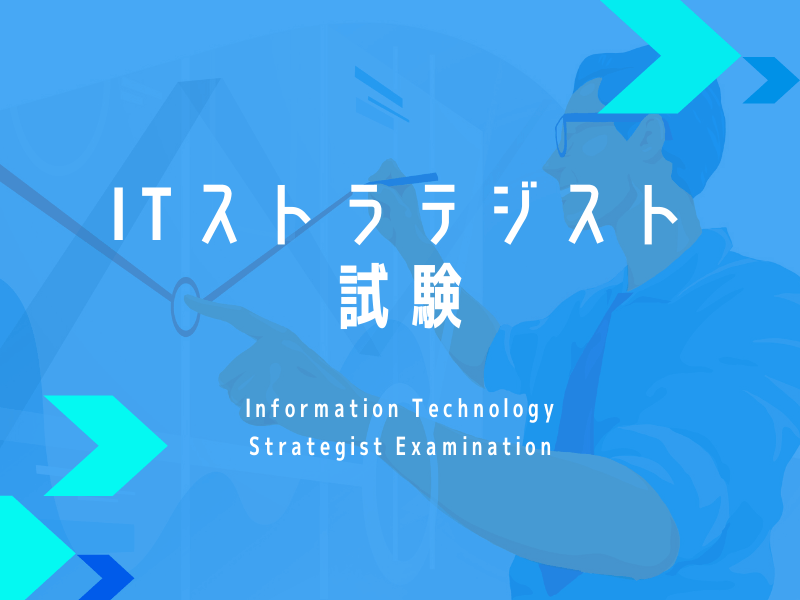
ITストラテジスト 試験 午後Ⅰ
特有の対策と必要な知識【令和元年更新】
これから開始する人、これまでに準備ができている人、それぞれの勉強法
これから試験対策を開始する人は、上記の Check-1. ~ 5. を進めていきましょう。
システムアーキテクト試験の受験生は、応用情報技術者試験をクリアした直後に受験する人が多く、しかも応用情報技術者試験レベルの知識と、それほど “知識面” では変わりません。
例えば、データベーススペシャリスト試験のように、新たに覚えなければならないことがあるわけではありません。
そういう意味では、 時間内に解ける解答速度があるかどうか が重要成功要因になります。
したがって、今からは徹底して時間を計測して解答する練習が必要でしょう。上記の Check-1. ~ 5. を意識しながら微調整すればいいと思います。
他方、これまでにCheck-1. ~ 5. の準備が出来ている人で、解答手順が確立している人は、もう午後Ⅰは OK かもしれません。
過去問題を “時間を計測して解いた数” にもよりますが、平成 25 年度~ 29 年度までの 5 年分ぐらい解答したのなら、それを再度、解く必要はありません。
ただし、解答したとき、解答を確認したとき、どうすれば速く解けるかを考えたときのことを、どれだけ覚えているのかを確認しましょう。
そして、問題文中にある解答の比率、表現のまとめ方なども再チェックしておくと万全だと思います。その上で、本番に向けた戦略を立てましょう。
label 午後Ⅱ [午後2] の論文対策はこちら

(ITストラテジスト/システムアーキテクト/ITサービスマネージャ 午後Ⅱ論文 [午後2] )

午後Ⅱ[午後2] ~論文に書くべきこと~
label システムアーキテクト 対策記事一覧 [令和元年]



『定額制』
高度試験対策研修 KOUDO 初公開!
定額制だから、どの区分でも何名でも受け放題!!
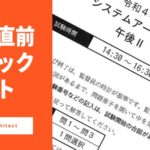
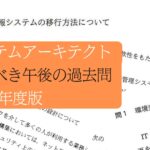
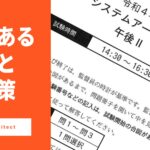


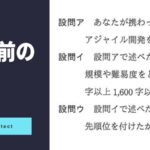
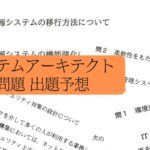

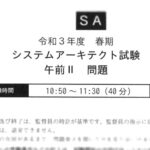


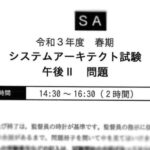

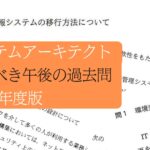

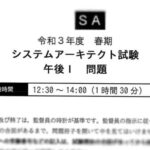

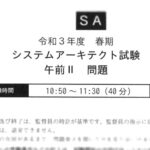
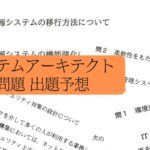


- 略歴
- 株式会社エムズネット代表。
大阪を主要拠点に活動するIT コンサルタント。 本業のかたわら、大手 SI 企業の SE に対して、資格取得講座や階層教育を担当している。高度区分において脅威の合格率を誇る。 - 保有資格
-
- 情報処理技術者試験全区分制覇(累計 32 区分,内高度系 25 区分)
- ITコーディネータ
- 中小企業診断士
- 技術士(経営工学)
- 販売士 1 級
- JAPAN MENSA 会員
オフィシャルブログ 「自分らしい働き方」Powered by Ameba