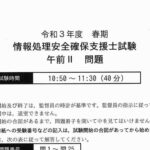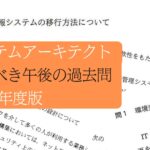プロジェクトマネージャ試験の過去問から見た特徴と対策
もくじ
午前Ⅱ[午前2] 過去問の出題傾向と突破率からみる特徴
過去 3 期の午前Ⅱ突破率( 午前Ⅱが 60 点以上の人 ÷ 午前Ⅱの得点ありの人 )は、78.8 % ~ 84.3 % です。毎回、おおよそ 8 割の人は午前Ⅱを突破しています。
出題される区分は、自区分(プロジェクトマネージャ)が 25 問中 16 ~ 18 問ぐらいで、他区分からは情報セキュリティが 2 問出題されています。令和 2 年の試験では、情報セキュリティの問題は 1 問増えるかもしれませんが、基本的には自区分の問題の比率が高い 試験区分になります。
また、PMBOK ® や JIS 規格に関する出題もあります。PMBOK ® (第 6 版)、JIS Q 21500:2018 などです。
午後Ⅰ [午後1] 過去問からみる特徴と解き方
プロジェクトマネージャ試験の午後Ⅰ試験には次のような特徴があります。
- 問題文が物語風の展開で、原則、時系列に展開している
- 設問も、問題文の展開に沿って順次問われていく
- 経験者が多いため、答えはある程度イメージが着くことが多い
- 何が問われているかが良く分からない問題も少なくない
- どうまとめればいいのかが悩みどころ
- 解答例を見れば「なんだ、そっちか!」というのが多い
プロジェクトマネージャ試験 午後 Ⅰ 問題の特徴
経験者が多く受験することや、イメージが着きやすいことから「全く知らない」、「全く手も足も出ない」ということはありません。
例年、受験生の 8 割以上の人が 50 点以上はあるので、不合格= 50 点台がデフォルトになるような時間区分なんですね。
そのため、上記のような 3. 4. 5. が悩みどころで、解答例を見て「おいおいそっちかい!だったら、もっとちゃんと聞いてくれよ . . . 」とツッコミを入れたくなるようなケースが多いのです。
逆に、そういうところにまで到達していなくて、解答例を見て感心したり「勉強になるわ」って感じたりする場合は、絶対的に知識不足だと考えなければならないと言えます。
したがって、プロジェクトマネージャ試験の午後Ⅰ対策を行う場合には、上記の 3. 4. 5. をしっかり考えた対策が必要で、それをしない限り “運” に左右されることになるので注意が必要です。
午後Ⅱ [午後2] 論文問題 の対策
プロジェクトマネージャ試験は、人気資格ということもあって「合格したい」という強い思いをもっている受験生が多いイメージがあります。
それゆえ、論文初挑戦の人でも、真面目に取り組んでしっかりと仕上げてきている人が多いと思います。そこに、再受験する人や、秋の試験で論文対策を行ってきた人が加わるため、原則は「しっかりと仕上げてきている人」の間での闘いだと考えてもらえればいいでしょう。
また、前述の通り、経験者が多い受験区分になります。
それに加えて、筆者の参考書(情報処理教科書 プロジェクトマネージャ)を使ってくださっている受験者が多く(販売部数から試算すると受験生の 6 ~ 7 割)、そこにいろいろ細かいテクニックを書いているので、(手前みそで申し訳ないのですが… )全体的なレベルが高くなっていると感じています。
実際、筆者が添削していても、初挑戦の人でも再受験される人でも、初回から( 1 本目から)「そこそこ程度のいい仕上がり」になっています。そこから仕上げていくわけですから、試験本番の時の出来の良さも想像できますよね。
以上のような状況なので、プロジェクトマネージャ試験の合格(論文だと A 評価)を目指すなら、ずばり「ちょっとした “差” 」を意識して、それを積み上げていって大きな差をつけるという”意思”こそが重要になります。
「仕事で成果を出しているから・・・」とか、「他の試験区分に既に合格しているから・・・」とかでしっかり仕上げてこない人は、苦戦を強いられることになるかもしれません。
「慢心が最大の敵!」・・・そう考えて、「ちょっとした “差” 」に目を向け、その「ちょっとした “差” 」を大切にし、「ちょっとした “差” 」をコツコツと積み上げていく人が合格に近い人だと思います。
どこから対策するか?
それではここで、この時期、何から着手するのがベストなのか? 考えていきましょう。
筆者は、間違いなく論文対策だと思っています。
全くの未経験者の場合は「基礎知識から」になりますが、ある程度の知識や経験がある人は、間違いなく午後Ⅱの問題文を読み込むところから始めるのがベストです。
そして「何が問われているのか?」を、できるだけ早い時期に(最初に)把握しましょう。進捗管理や品質管理などテーマごとに「午後Ⅱで問われるポイント」というのがありますからね。そこをいち早く把握しておくところから始めます。
そして「何が問われているのか?」を把握できれば、書ける、書けないの判断をして、書けないものに対しては、午後Ⅰの問題を解きながら「あ、午後Ⅱのあの問題のネタに使えるぞ」という感じで理解を深めていきましょう。
論文が書けるようになるのは先でもいいので、まずは「何が問われているのか?」を把握するまで午後Ⅱを読み込んで、そのあとに午後Ⅰに着手して並行して進めていきましょう。午前Ⅱは最後の最後,直前でも構いません。
navigate_next
navigate_next
具体的な練習方法は次の機会に。それまで、市販の試験対策本を使って学習を進めておきましょう。
label 関連タグ『定額制』
高度試験対策研修 KOUDO 初公開!
定額制だから、どの区分でも何名でも受け放題!!
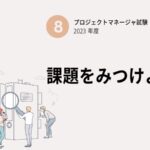
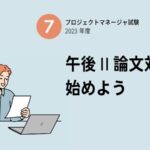
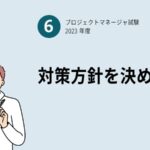
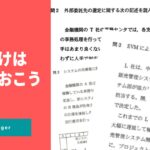
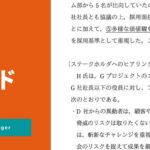
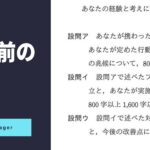


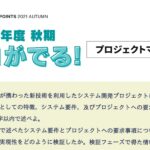
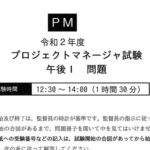
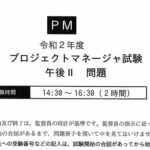

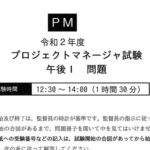





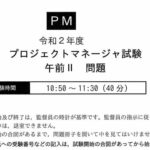


- 略歴
- 株式会社エムズネット代表。
大阪を主要拠点に活動するIT コンサルタント。 本業のかたわら、大手 SI 企業の SE に対して、資格取得講座や階層教育を担当している。高度区分において脅威の合格率を誇る。 - 保有資格
-
- 情報処理技術者試験全区分制覇(累計 32 区分,内高度系 25 区分)
- ITコーディネータ
- 中小企業診断士
- 技術士(経営工学)
- 販売士 1 級
- JAPAN MENSA 会員
オフィシャルブログ 「自分らしい働き方」Powered by Ameba