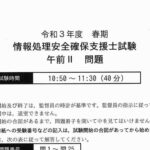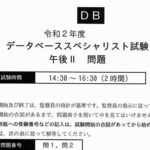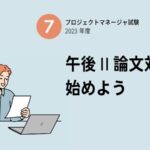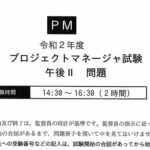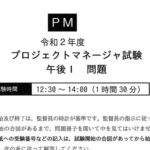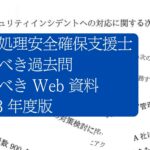残り2週間でゼロから始める基本情報技術者試験「午前」の勉強方法
もくじ
これから開始する人、及び現段階で全然仕上がっていない人
これから試験対策を開始する人や、全然午前が仕上がっていない人は、残り2週間、次のような方針で合格を狙いましょう。
-
試験2週間前から準備ゼロではじめる基本情報技術者試験対策
- (1) 今からは、試験対策本を使わずにIPAの公表している過去問題だけを利用する
- (2) 理解していないと解けない問題(計算問題、規則性のある問題)の理解は捨てる
- (3) 解説の必要ない問題(覚えるだけの問題)に的を絞って、より多くのことを覚える
まず、残り2週間になると、1問に時間をかけることができません。最低でも500問ぐらいの問題には目を通しておいた方がいいからです。
(1) 今からは、試験対策本を使わずにIPAの公表している過去問題だけを利用する
まずは、その500問以上の過去問題を手に入れます。
今お使いの参考書は何ページありますか? 過去問題集は過去何年分ありますか?
参考書だと10分冊以上で総計1000ページぐらい、過去問題集は10年分20期分ぐらいありますか?
あれば(その分量をこなせる時間もあれば)問題ありませんが、無ければIPAの問題と解答例だけの “シンプルな学習ツール” を使いましょう。
IPAが公開している過去問題のページには平成16年度以後の過去問題があります。
このうち、平成21年度から平成30年度秋期までの20期分(1期80問なので1600問)の問題を対象にします。もちろん余裕があれば平成16年度~平成20年度までの問題まで手を広げても構いません。それが一応、MAXになります。
最初にそれをダウンロードします。可能であれば…(大量でも問題無ければ)、プリントアウトしたいところです。
20期分でも1600問全部を覚えるというわけではありません。
そして、順番に目を通していきます。
「え?20期分?1600問?できるかな?」
なんて億劫に思うかもしれませんが、1600問全部に時間を均等にかけるというわけではありません。
その20期分の中には同じ問題が繰り返し出題されているものがあったり、後述するように一部の問題はスルーしたりするからです。
おそらく、時間をかけて覚える問題は500問ぐらいになるのではないでしょうか。
(2) 理解していないと解けない問題(計算問題、規則性のある問題)の理解は捨てる
過去問題に目を通して行く時、次の点に留意しましょう。
- 多くの問題に、かつ何度も繰り返しチェックできるように、1問に時間をかけないこと
- 1問1分程度にすること
- 理解に時間のかかる計算問題や、規則性のある問題はスルーすること
理解していなければ解けない問題や、解説が無いとなぜその答えになるのかわからない問題は、原則無視で構いません。
全く同じ問題が出ることもあるので、時間をかけないことを前提に、解答だけを(意味も分からないまま)覚えておくぐらいなら構いませんが…
なんせ理解している時間が無いので、理解する必要がある問題スルーするしか無いのです。
思い切って無視しましょう。
というのも…実は、無視しても大丈夫なんです。
午前問題80問の中に、計算問題、規則を覚えておかないと解けない問題、「なぜ、その解答になるのか?解説が無いとよくわからない」という問題…すなわち、IPAの問題と解答の“記号”だけでは意味不明の問題はそんなに多くはありません。
例えば、前回の平成30年度 秋期 の午前問題(全80問)で、そういう問題は23問です。3割もありません。
あとの57問(約7割)は、
「SFAの説明はどれか?」とか、
「…を何というか? 答えはSFA」とか、
問題文と解答を見て…
“理解”ではなく、”覚えておく”問題です。別の言い方をすれば「なぜその答えになるのか?」という解説が必要のない…IPAの公開している過去問題と解答例だけで学習できる問題なのです。
「ただ覚えるだけ」
もちろん、IPAの公開している問題と解答だけだと、深い理解は期待できませんし、誤解したまま覚えてしまうという弊害もあります。
しかし、それは、後述するように試験が終わってからキャッチアップしていけばいい話です。
残り2週間、合格だけを狙うのなら…一時的にそこを捨てるという戦略しかありません。
ということで、過去問題20期分に目を通すひ必要があるので、計算問題、規則を覚えておかないと解けない問題、「なぜ、その解答になるのか?解説が無いとよくわからない」という問題(約3割)は無視して進めましょう。
(3) 解説の必要ない問題(覚えるだけの問題)に的を絞って、より多くのことを覚える
そうして、解説が無くてもただ覚えるだけの問題、すなわち“用語の意味を知っていれば解ける問題”や“用語の特徴を知っていれば解ける問題”だけに的を絞って、片っ端から覚えていきます。
試験本番でも、そこで確実に点数が取れるようにしておくというわけです。
これまである程度準備が進んでいる人
これまで準備が進んでいる人も、先に説明した方法で「知らない用語」を無くし、解ける問題を増やしていく戦略が必要かもしれません。
その場合は、同じような方法で進めていっても構いませんが…
やはり、しっかりと準備してきた人の強みは…これまで時間をかけて理解してきた計算問題や規則性のある問題、解説が無いとなぜその解答になるのかわからない問題が解けるという点になりますから…
これまで通り、
“理解している問題を増やしていく”
という学習を中心に据えて進めていきましょう。
但し、試験が終わってからの復習を忘れないように
残り2週間、午前は、このように計算問題等を無視して、用語の意味を片っ端から覚えていく…いわば“付け焼刃的に”60点を狙うことができます。
しかしその場合、深く理解していないまま“正解してしまう”ことになり、それで“合格してしまう”こともあります。
それはそれで嬉しいことなのですが、そのまま放置しておくと、いろんな意味で残念です。
そこで、試験が終わった4月21日から間を空けずに、本番試験で出題された問題については、じっくりと時間をかけて深く理解するところまで復習をしておきましょう。
試験は終わっているので時間はたっぷりあります。しかも出題された問題だけなら数も限られています。
それゆえ、一つのテーマに10時間でも20時間でもかけたれますからね。
計算問題はその計算式や考え方を、規則性のある問題はその規則性を、解説が必要なものはネットで検索するなどして、徹底的に理解を深め、より詳しい知識を身に付けるようにしましょう。
それが完了した時に初めて、合格に値する知識が身に付いたことになるでしょう。
label 関連タグ『定額制』
高度試験対策研修 KOUDO 初公開!
定額制だから、どの区分でも何名でも受け放題!!





















- 略歴
- 株式会社エムズネット代表。
大阪を主要拠点に活動するIT コンサルタント。 本業のかたわら、大手 SI 企業の SE に対して、資格取得講座や階層教育を担当している。高度区分において脅威の合格率を誇る。 - 保有資格
-
- 情報処理技術者試験全区分制覇(累計 32 区分,内高度系 25 区分)
- ITコーディネータ
- 中小企業診断士
- 技術士(経営工学)
- 販売士 1 級
- JAPAN MENSA 会員
オフィシャルブログ 「自分らしい働き方」Powered by Ameba