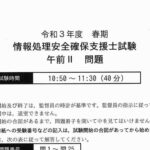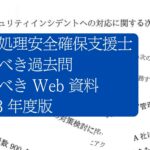システム監査技術者 試験 残り10日でする直前対策
さぁ、いよいよ試験まで残り 2 週間をきりました。もう受験票も届いていると思います。土日はあと 1 回。最終の超直前点検として、残り 10 日間程度でできる最終チェックを行いましょう。
受験するかどうかは当日判断
まずは大前提。 10 月 18 日は受験しましょう!
と、いつもなら言ってるところですが…今年は若干事情が違います。
今回は、当日の検温が義務付けられています。当日の朝、熱があると( 37.5 度以上の場合)受験できません。それに、当日体調がすぐれなければ受験を控えたほうがいいかもしれません。疲労がたまっていると免疫が低下しているかもしれませんからね。受験会場に行っても、そこが危険な場所だと判断したら、その時点で帰宅した方がいいでしょう。
いずれにせよ、今年は無理は禁物です。長期的視点で考えて、冷静に判断しましょう。
午後Ⅱ [午後2] 論文対策
これまで順調に論文対策を実施されてこられた方は “試験前の総点検” として、下記のポイントを確認しましょう。
- “監査手続” の表現は固まっているか?
- 監査手続につなげる “リスク” と “コントロール” の意味を理解しているか?
通常、システム監査技術者試験の午後Ⅱ論文試験で、設問イや設問ウで “監査手続” が問われている問題は、ザックリ言うと次のような構成になっています。
- 実施したいことや目標
- それに対するリスクとリスク要因
- 2. に対するコントロール(監査人の考え or 実施しているコントロール)
- 3. に対する確認(監査手続)
したがって、問題文と設問を読む時に、上記の 1. ~ 4. を(設問ア、イ、ウの)どこに書けと指示されているのかを読み取って、指示されている場所を間違わないようにしなければなりません。そうしないと、出題者の考える論旨展開にならないからです。
個々の設問で、 “リスク” や “コントロール” が明確に問われている場合はいいのですが、それが明確に求められていない場合は、書かなくてもいいのか、それとも書いた方がいいのか、はたまた書いた方が良いのなら、それはどれくらいの分量がいいのか?などを考えなければなりません。原則は、 “明確に” 問われていなくても、リスクとコントロールは、個々の監査手続の合理性を示す根拠になるため、書いた方が良いと考えましょう。
また、注意が必要なのは…システム監査人は第三者の立場なので、 “リスク” と “コントロール” には、監査人が必要だと考えるものと、当時者が認識している “リスク” や、実施している “コントロール” の 2 種類があることです。設問では、どっちが問われているのかを読み取って正確に述べる必要があります。
監査手続に監査証拠を含めて表現するということ自体、その監査証拠は予備調査で確認した当該当時者が実際に使用しているものです。監査人が「きっとこういうドキュメントがあるだろう」ということで憶測の下に語っているわけではありません。そのドキュメントが無ければ、その監査手続自体が破綻するわけですからね。したがって、監査手続の前には、
というように、実際に当事者が実施しているコントロールを書いてから、それに対する監査手続を書くことになることが多くなります(仮に、予備調査でコントロールが確認できなければ、コントロールの有無を確認するという監査手続になります)。
しかし、問題によっては…
というように問われているケースもあります。これはどう考えても監査人の考えるコントロールです。その場合は、特定の手段に限定してはいけないために(実施しているコントロールは特定の手段に限定されるのに対し)、 “手段” の部分は抽象的な表現になるでしょう。イメージとしては「何かしらの方法で」という感じです。
いずれにせよ、そういう部分が求められているのかどうかを読み取る必要があるわけです。そのあたりの違いを考えながら、適切に会話のキャッチボールができるように考えていきましょう。
なお、これまであまり勉強できなかった受験者は、上記の視点で何かしらのサンプル論文を読んで、感覚だけでもつかんでおきましょう。
午後Ⅰ [午後1] 対策
システム監査技術者試験の午後Ⅰ試験は、ザックリ言うと、他の論文系試験区分のテーマに対しての監査なので、次のような分類が可能です。
- 特定システム企画時のシステム監査
- 特定システム開発時のシステム監査
- 特定システム開発時のプロジェクトの監査
- 特定システムの運用時の監査
- 特定システムのセキュリティ監査
したがって、午後Ⅰ試験で問われるのは下記の 3 点です。
- システム監査手順
- システム監査特有の表現(言い回し)
- 他の試験区分( ST, SA, PM, SM, SC )の知識
このうち 1. と 2. は、午後Ⅱ対策でも必要な要素なので、そこが問題無ければ、今後は特に対策は必要ないでしょう。
これまで、試験対策を進めてきた人は、今まで覚えてきたことを思い出すことに専念するくらいで大丈夫です。日記のように手帳にスケジュール等を書き込んでいる人は、それを頼りに思い出すのでも構いません。思い出すだけなら脳内だけできるので、いつでもどこでも…ちょっとした数分間でもできますよね。それを徹底的に。思い出せなかったものはノートや参考書、過去問題などを再度確認しましょう。
午前Ⅱ [午前2] 対策
午前Ⅱ対策は、直前勝負になります。
システム監査技術者試験の午前Ⅱ試験では、自区分(システム監査分野)の問題が他の試験区分に比べて少ないのが特徴です。
例年、 25 問中 10 問ぐらいしか出題されません。たった 4 割です。
とは言うものの、この 10 問を確実に押さえていくことが重要なので、今の試験体系に変わった平成 21 年から 10 年分でもわずか 100 問です。これは絶対に目を通しておいて、確実に解けるようにしておきましょう。いくら時間が無くても…最低限ここは、やっておかないといけないところになります。
但し、平成 30 年、 15 年ぶりに「システム監査基準」及び「システム管理基準」が改訂されています。したがって、古い問題は若干注意が必要です。
平成 29 年以前の午前Ⅱ問題で、解答が変わるほどの問題はほとんどありませんが、監査基準の表現が変わっている場合や、もう出題されない問題はあるので、そこは新基準に置き換えて判断することが必要です。新基準をベースにすると過去問題がどうなるのか(どこがどう変更されるのか)を考えながら進めていきましょう。
そして、残りの 15 問(他区分の問題)ですが…まずはシステム監査技術者試験の午前Ⅱで出題されている問題からチェックします。そして時間的に余裕があれば(今からだと時間的にちょっと厳しいと思いますが)、応用情報の過去問題までチェックしておけば万全です。
以上で、残り 10 日間の準備は万全です。可能な範囲で仕上げていきましょう。
label 関連タグ『定額制』
高度試験対策研修 KOUDO 初公開!
定額制だから、どの区分でも何名でも受け放題!!
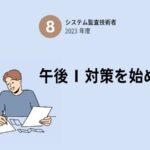

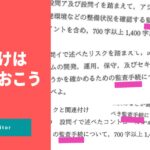
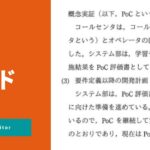



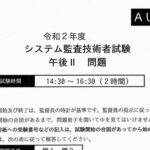

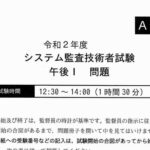




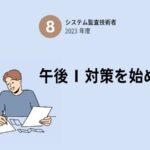


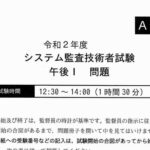



- 略歴
- 株式会社エムズネット代表。
大阪を主要拠点に活動するIT コンサルタント。 本業のかたわら、大手 SI 企業の SE に対して、資格取得講座や階層教育を担当している。高度区分において脅威の合格率を誇る。 - 保有資格
-
- 情報処理技術者試験全区分制覇(累計 32 区分,内高度系 25 区分)
- ITコーディネータ
- 中小企業診断士
- 技術士(経営工学)
- 販売士 1 級
- JAPAN MENSA 会員
オフィシャルブログ 「自分らしい働き方」Powered by Ameba