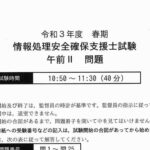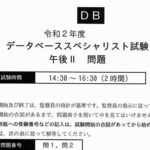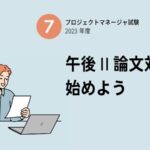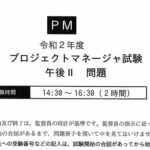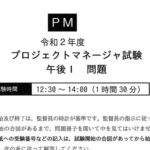システム監査技術者 2022 年度 9 月は午後Ⅱ(午後2)論文対策を極めよう
まもなく 9 月になります。 10 月 9 日の試験まで残り約 1 か月です。 試験対策は順調でしょうか? 夏季休暇でリフレッシュできた人も、そうでもなかった人も、今回は「これだけはやっておこう!」をテーマに記事にしてみました。
順調に来ている人はその確認を、思うように進んでいない人はこれをきっかけに合格目指して頑張りましょう。 まだラストスパートは必要ないので、今回は気楽にチェックしてみてください。
進捗の確認
今回も、まずは進捗の確認です。 全体スケジュールと照らし合わせて、これまでの進捗状況を確認してみましょう。
info 学習スケジュールに関する記事

順調であれば、既に午前Ⅱ対策、午後Ⅰ対策が進み、午後Ⅱ対策も「問題文の読み込み」がひととおり完了し、論文準備に着手したころではないでしょうか。
それを踏まえて、これから実施する残り 1 か月間の対策を考えましょう。
午後Ⅱ対策を極める!
残り 1 か月は、本格的に論文を仕上げていく時期ですが、いかがでしょう? 論文は、もう既に、十分仕上がって … 自信がもてるレベルになっていますか?
「はい。 問題ありません。 順調です。 」という人はさておき、「いえ、まだまだで、かなり焦っています。 」という人は、今からここで説明する対策を検討してみてください。
1 一般論ではなく「今回の固有の事例」にする
論文添削をしていて、最も頻繁に指摘していることが「一般論になっている」という点です。 したがって、まずは自分の書いた論文が「一般論」になっていないかどうかをチェックして、(一般論になっていたら)改善するところから始めましょう。
システム監査技術者試験を受験される人は、同時期に開催されるプロジェクトマネージャ試験に合格されていたり、他の論文試験に合格したりしている人が多いので、知識は十分にあるんですよね。 したがって、最初から「一般論」としては、とてもよく書けているんです。 問題文にもそこそこ例が出ていますし。
しかし、皆さんご存知の通り、情報処理技術者試験の午後Ⅱ論文試験では、どの試験区分においても “一般論” を書くのは御法度です。 自分が経験した自分の経験を書かないと合格論文にはなりません。
そこで、一般論にならないようにしなければならないのですが、システム監査技術者試験の場合、どこを「今回の事例」にしたらいいのか、わかりにくくなっているので、混乱するわけです。
システム監査技術者試験の論文では、次のような点を自分自身の「今回の事例」として書きます。
- looks_one リスク
- 設問アで書いたことに対して固有になる。
- looks_two 実際に実施されているコントロール
- コントロールの適切性に関する監査の場合に限りますが、その場合は、当事者が実施しているコントロールが固有です。
2 リスク・コントロール・監査手続の表現を固める
次に考えるのは、リスク・コントロール・監査手続の表現を固めることです。
例年、少なくとも 1 問は「監査手続」について問われていますよね。 ある程度、午後Ⅱの過去問題に目を通していたら、気付いているはずです。 そして、監査手続が問われている問題では、リスク・コントロール・監査手続の流れになっていることも確認できているでしょう。
そこで、まずは頻出の「監査手続」の問題にしっかり準備することが王道です。 実際、筆者が実施している添削サービスでも、こうした「監査手続」の問題から仕上げることを推奨しています。
ただ、注意すべきことがあります。 それは、特定の過去問題に対してコンテンツ(論文ネタ)を準備するというやり方では、苦戦するという点です。
システム監査技術者試験の場合、対象システム、監査をするタイミング(企画段階、運用段階など)、監査の観点(適切性、有効性など)など、すべての要素がまったく同じになるような問題はほとんど出題されないからです。
午後Ⅰの問題の事例と午後Ⅱの問題で問われているケースも何かしら違っていますからね。 そのままでは参考にならないのです。
とはいうものの、午後Ⅱ試験対策において午後Ⅰの過去問題ほど役立つツールはありません。
そこで、午後Ⅰの過去問題を活用して、リスクの表現や内容、コントロールの表現や内容、監査手続の表現や内容を参考に、それぞれ、どういう要素を使ってどういう表現をしているのか、把握することをお勧めします。
具体的には、一度時間を計測して解いてみた午後Ⅰの過去問題を再度引っ張り出し、その問題文の中に記載されている「リスク」、「コントロール」、「監査手続(監査要点、監査証拠、監査技法を含む)」をピックアップします。 そして、それぞれの関連性(リスク → コントロール → 監査手続の流れ)を確認し、表現を覚えましょう。 ノートに整理しながら進めることも、とても効果的だと思います。
要するに、次のような順番で試験対策を進めます。
- 午後Ⅰの過去問題を、時間を計測して解いてみる(=午後Ⅰ対策)
- 午後Ⅰの過去問題を、リスク・コントロール・監査手続に分けてチェックする
(ノートに整理する)
これ以外にも、まだまだ準備しておきたいことはあると思います。 監査手続以外の問題への備えも必要だと感じている人もいるでしょう。
しかし、それは … あくまでも「監査手続」の問題が仕上がってからの話。 まずは、オーソドックスな「監査手続」の問題から極めましょう。
label 関連タグ『定額制』
高度試験対策研修 KOUDO 初公開!
定額制だから、どの区分でも何名でも受け放題!!
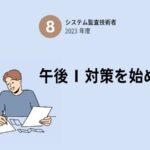

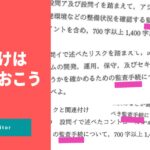
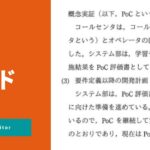



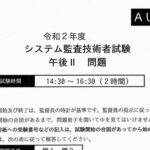

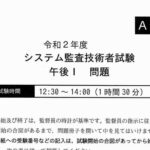

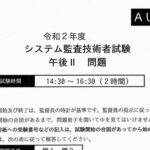


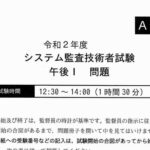


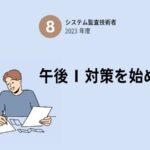



- 略歴
- 株式会社エムズネット代表。
大阪を主要拠点に活動するIT コンサルタント。 本業のかたわら、大手 SI 企業の SE に対して、資格取得講座や階層教育を担当している。高度区分において脅威の合格率を誇る。 - 保有資格
-
- 情報処理技術者試験全区分制覇(累計 32 区分,内高度系 25 区分)
- ITコーディネータ
- 中小企業診断士
- 技術士(経営工学)
- 販売士 1 級
- JAPAN MENSA 会員
オフィシャルブログ 「自分らしい働き方」Powered by Ameba