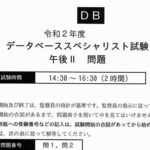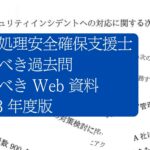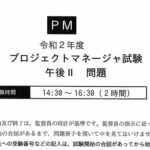システム監査技術者の対策準備 2022 年度 ~6月は専門用語とDXに関するWeb資料を確認しよう
さぁ 6 月になりました。 今月を含め試験まで約 4 か月です。
一般的に、企業で開催する試験対策講座は 7 月中旬から始まります。 それゆえ、この 6 月という時期は … ほとんどの人が、まだ始動していません。 モチベ―ションの高い人は、既に学習を開始しているでしょうが、それでも … 少なくとも “プロのノウハウ” を得て急成長する時期ではありません。 プロ野球で例えると、ちょうど … キャンプインするまでの自主トレ期間のようなものですよね。
6 月の方針
この自主トレ期間に何をするのかはこの後じっくり考えるとして、少なくとも “心に余裕をもつ” ことはできるのではないでしょうか。 周りが止まっているわけですからね。
試験を(絶対評価とはいえ)相対的なものだと考えれば … この時期、どんなことをしてもプラスになります。 差が詰まる、差を広げることができます。
したがって、 “合格まで遠いかな” と思う人は「今の間に追いつくぞ」という方針で、 “合格に近い” と思っている人は「今の間に差を広げよう」という方針で、それぞれ学習を進めていくといいでしょう。
全体スケジュールの確認
続いて、全体スケジュールを以下の記事で確認しましょう。
info 学習スケジュールに関する記事

上記の記事は、原則 “未経験者” を想定して書いているのですが、経験者の方はその先に進めていても問題はありません。 ポイントは、早い段階から午前Ⅱ・午後Ⅰ・午後Ⅱを同時並行的に進めるという点です。
まずは、システム監査基準とシステム管理基準の理解しながら、一連の監査手順を覚えていきます。 その後、監査特有の専門用語を覚えることを目的に、午前Ⅱ対策(特に、システム監査基準、システム管理基準、用語の説明に関連している基本的な問題)に着手します。
午前Ⅱ対策を通じて、ある程度監査特有の専門用語を覚えられたら、システム監査の手順が把握できたと言えるので、午後Ⅱの問題文の読込みに入ります。 どのようなことが取れているのかを把握するのが最大の目的なので、「難しいな」とか「書けないな」と感じるだけでも構いません。
さらに、それぞれの専門用語が、実際どのように使われているのかを把握するために、午後Ⅰ対策へ進めるという流れです。
システム監査手順及び監査特有の専門用語を覚える
システム監査技術者試験対策は、次の 3 点から着手することを進めています。
- システム監査とは何かを把握する
- システム監査手順の流れを把握する
- システム監査特有の専門用語を覚えて理解する
そのために、目を通しておくべきものは、次のようなものです。
この二つの資料をベースに、そこに出てくる監査特有の専門用語について、ご利用中の参考書を使って、よりしっかりと把握します。
なお、システム監査基準及びシステム管理基準について、現在の最新版は平成 30 年 4 月に公表されたものです。 したがって、それ以後に刊行された参考書であれば最新版と同期がとれていると思われますが、古い参考書をそのままお使いの場合は、対応できていない場合があります。 注意しましょう。
午前Ⅱ対策
システム監査特有の専門用語をある程度覚えたら、午前Ⅱの過去問題も併せてチェックするといいでしょう。
午前Ⅱの過去問題のうち、用語の説明をしている問題や、システム監査基準及びシステム管理基準に関する問題だけに絞り込めば、それほど時間はかからないと思います。
DX 関連知識とアジャイル開発に関する知識
平成 30 年の午後Ⅱ試験では、他の試験区分に先駆けて DX 関連ではないかと思える問題が出題されました。 問 1 の「アジャイル開発に関するシステム監査」です。
その後、平成 31 年には「 IoT システムの企画段階」、令和 2 年には「 AI 技術を利用したシステムの企画・開発」、令和 3 年には「 RPA ツールを利用した業務処理の自動化」の問題が出題されています。
平成 30 年から 4 年連続で DX 関連(先端技術含む)だと思われる問題が出ています。
一方、午後Ⅰ試験でも、平成 31 年以後、毎年 1 問は DX 関連(先端技術含む)だと思われる問題が出ています。
これはおそらく、 DX 関連システムが(従来のシステムに比べて)、より “不確かさ” を含むため、企画段階や計画段階でシステム監査の果たすべき役割が大きいと考えているからかもしれません。
そこで、この時期に DX 関連知識やアジャイル開発に関する知識をストックすることをお勧めします。 参考までに、筆者がお勧めする資料を 3 つほど紹介します。
上記以外にも様々な資料や書籍が出ていますが、やはりここは(試験の主催者である) IPA が公表している資料でしょう。 試験対策に限っては、最も信頼がおけるからです。
午後Ⅱ対策
この時期の午後Ⅱ対策は、どういう問題が出ているのか知るだけで十分です。
システム監査経験者や 2 回目以上の受験で、これまで説明してきたところに課題が無い場合や、添削指導を受けている場合を除き、まだ論文を作成する必要はないでしょう。 というよりも、まだ精度の高い論文は書けないと思います。
そうではなく、今後何を勉強していけばいいのか?何が足りないのか?という課題を知ることを最大の目的に、問題文の読込みを進めるとよいでしょう。
午後Ⅰ対策
その後、午後Ⅰ対策に着手していきます。
ある程度、監査手順や監査特有の専門用語を把握し、午後Ⅱ問題をチェックして、どの部分がどれくらいの割合で問われるのか確認できれば、午後Ⅰ対策も進めましょう。
午後Ⅰで点数を取る目的だけではなく、(ある程度、午後Ⅱ問題が頭の中に入っていると)午後Ⅱのネタにしたり、午後Ⅱで問われている「表現レベル」を把握も目的にするとよいでしょう。
なお、具体的な午後Ⅰ対策は、こちらを参考にしてください。
info 午後Ⅰ対策に関する記事
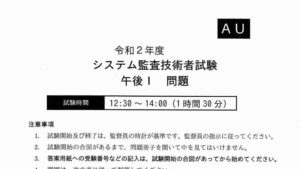
『定額制』
高度試験対策研修 KOUDO 初公開!
定額制だから、どの区分でも何名でも受け放題!!
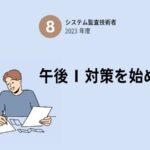

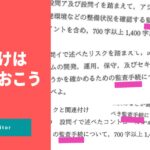
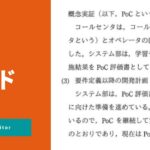



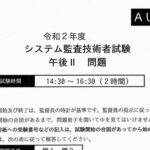

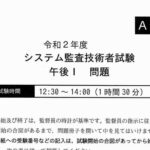


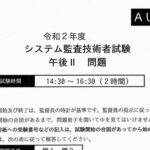
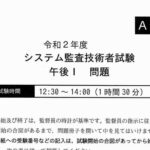







- 略歴
- 株式会社エムズネット代表。
大阪を主要拠点に活動するIT コンサルタント。 本業のかたわら、大手 SI 企業の SE に対して、資格取得講座や階層教育を担当している。高度区分において脅威の合格率を誇る。 - 保有資格
-
- 情報処理技術者試験全区分制覇(累計 32 区分,内高度系 25 区分)
- ITコーディネータ
- 中小企業診断士
- 技術士(経営工学)
- 販売士 1 級
- JAPAN MENSA 会員
オフィシャルブログ 「自分らしい働き方」Powered by Ameba