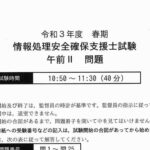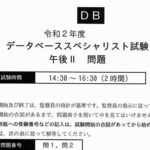2018年度春期 プロジェクトマネージャ試験 午後Ⅱ 問2
もくじ
過去問題との関係性
平成19年度の問2…そのまま。よかった… ◎付けていた。
- 状況(問題)は同じもので可能
- 対応策も同じもので可能
但し,平成19年度問2の方が問題文に詳しく書いてくれているので,この問題で論文を準備していた人は…そのまま使えたと思う。
また,平成19年問2の元になった問題が平成12年問3。これも同じ問題。
したがって,お持ちであれば、情報処理教科書プロジェクトマネージャの平成19年問2の解説を確認して欲しい。
設問ア
1-1.プロジェクトの特徴
これは稼働開始日(○月×日で)厳守とその理由で大丈夫。
1-2.問題の発生
次のところを具体的,定量的に。
- 問題発生日(稼働開始日までの期間も書いておくと臨場感)
- 問題の内容(機能面、性能面、業務運用面などのいずれか)
- 稼働開始日までに解決できないと判断した理由
※解決までの工数と日数の見積もりはここでした方がいい。それを理由とする。ここで例えば稼働開始後1か月とすると…
設問イ
2-1.問題の状況把握と影響分析
いずれも“どのように”と聞かれているので,状況把握のプロセスと影響分析のプロセスについて言及しないといけない。また“関係部門とともに”と書いているので(これはH19-2も同じ),関係部門を具体的部門として,どの部門とともに,どういう手順で状況把握と影響分析をしたのか?その結果,どのような状況で,どのような影響があるのか?までを書く。
ただ,ここではまだ部分稼働も何も対策が決まっていないので,その課題を残したまま本番稼働を開始して,例えば解決までの期間が1か月間であれば,その影響について書く。
問われ方は違うが,問われていることはH19-2と同じ。
2-2.当面の対応策
この問題文にも若干の例があるが,だいたいこんな感じ。H19-2の問題文中には,もう少し詳しく載っている。
関係部門との調整や合意の内容も含めてとあるので,利用部門や運用部門へのお願い,つまりいわゆる「運用で逃げる」方法で一時しのぎをする。
ここもお持ちであれば、情報処理教科書プロジェクトマネージャのH19-2の解説を参照。
あとは計画的表現(いつからいつまで,誰が(何人が),何をどのようにどうするのか?その理由は?)にすれば万全。
設問ウ
まずは実施状況。特に問題なく関係部門と連携しながらなんとか乗り越えたテイストで書く。
後は,平成20年以前と同じ「評価と改善点」。
評価に関しては,「しっかりと影響分析したことで,そこに要員を配置し,暫定的な対応策でも問題なく1か月間切り抜けた。こういう時に,影響分析をして影響範囲を特定することの重要性を改めて認識した。」みたいなことを書いておけばいいだろう。基本は設問イで実施したことを書いておけば大丈夫。
改善点は,「遅れないようにしよう」という…本稼働間近で発見された問題についての改善点を書いてしまいがちだが,それは採点講評で指摘されるだろう。
そうではなく…ここは設問イの改善点。なので当たり障りのない「関係部門を巻き込むわけだから,段取りよく,効率よく進めていこう」という方がマシである。
ベストは…コスト面などに言及することだろうか。責任の所在にもよるが,この問題のパターンだとどっちでも行けそうだ。機能面,性能面の不備の判明はベンダ側だが,業務運用面の整備が進んでいない状況は利用者側の責任。
前者の場合,例えば1か月間要員を2名立ち合うように指示したけど1人で良かったとか,いや3人にした方が良かったなど。
暫定的対応策の時に,コスト面を当面置いといて対応することが多いので,暫定的対応策は成功したけど,もうちょっとコストは抑制できたかな?程度で行くと現実的。
感想
こちらを選んだ人が多いはずで、全体的に出来はいいはずなので、激戦だろう。
私の論文添削でH19-2のA評価を貰っている人は,そのまま書いたらハイレベルで合格。
設問イの暫定的対応策が計画的表現であればまずは一安心。後は,問題文に全く出てきていないコスト面を設問イや設問ウで触れていれば万全だろう。
これらがいずれもできていない場合でも下記の4つのポイントさえ押さえておければ,十分A評価は可能だと思われる。
- 関係部門を具体的に。部門の人数や代表者の A さん、B さんが欲しいところ
- 時間軸をこれだったら日付ベースでほしい。稼働開始日、問題の発生日、完全解決予定日などは必須。
- 状況把握と影響分析のプロセス(どのように)
- 状況、影響を具体的に
あくまでも,過去問題を添削してみて掴んでいる合格水準なので,予想だが。
参考資料
プロジェクトマネージャ(PM)には,システム開発プロジェクトで発生する問題を迅速に把握し,適切な解決策を立案,実施することによって,システムを本稼働に導くことが求められる。しかし,問題の状況によっては暫定的な稼働とせざるを得ないこともある。本問は,稼働日の延期が難しい状況にあるときに,本稼働間近で稼働日までに解決が困難な問題が発見された場合,利用部門や運用部門などの関係部門と調整し,合意を得ながら,暫定的な稼働に至るために立案,実施した当面の対応策について具体的に論述することを求めている。論述を通じて,PMとして有すべき問題解決に関する知識,経験,実践能力などを評価する。
著者の三好康之さんから許可を得て、2018年度 春期 情報処理技術者試験 の出題問題への感想を一部修正し、転載しています。
転載元: 三好康之オフィシャルブログ 「自分らしい働き方」Powered by Ameba
label 関連タグ注: 文中に出る (**章) は 情報処理教科書 プロジェクトマネージャ の該当章を指しています
『定額制』
高度試験対策研修 KOUDO 初公開!
定額制だから、どの区分でも何名でも受け放題!!
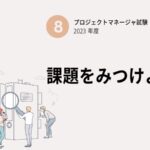
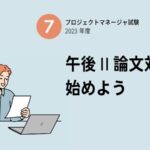
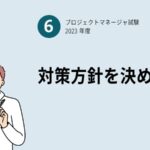
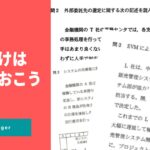
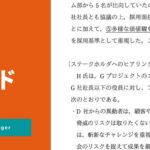
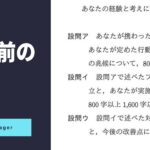


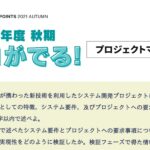
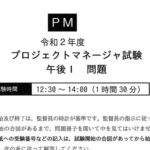
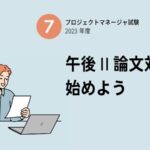
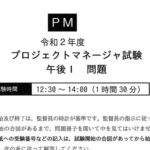
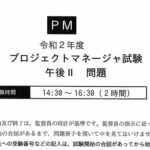

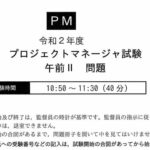

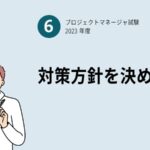
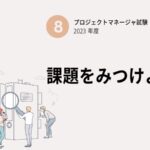
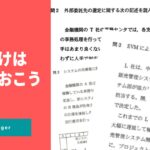


- 略歴
- 株式会社エムズネット代表。
大阪を主要拠点に活動するIT コンサルタント。 本業のかたわら、大手 SI 企業の SE に対して、資格取得講座や階層教育を担当している。高度区分において脅威の合格率を誇る。 - 保有資格
-
- 情報処理技術者試験全区分制覇(累計 32 区分,内高度系 25 区分)
- ITコーディネータ
- 中小企業診断士
- 技術士(経営工学)
- 販売士 1 級
- JAPAN MENSA 会員
オフィシャルブログ 「自分らしい働き方」Powered by Ameba