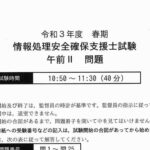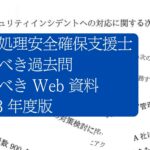システム監査技術者 対策 午後Ⅱ[午後2]過去問を使った論文対策
それでは、システム監査技術者の午後Ⅱ論述試験対策を見ていきましょう。学習が進んでいない人はこれからの3週間の進め方の参考に、学習が進んでいる人は現段階でのチェックに活用してみてください。
もくじ
Check-1. “監査手続”の表現は固まっていますか?
まずはここからです。
システム監査技術者試験の午後Ⅱの過去問題を見ていただくと明らかですが、 最も頻繁に出題されているのは“監査手続” を答えさせる問題です。ある意味、デフォルトだと言っても過言ではありません。
したがって、最初に着手するのは(そういう “監査手続” が問われている問題に備えて) “監査手続” を論述できるように仕上げていくことになります。
そのあたりはいかがでしょうか?
監査手続の表現は固まっていますか?
なお、“監査手続” の表現は、午後Ⅰ試験の過去問題を参考にするのがベストです。
午後Ⅰの問題では、下記の例のように監査手続の例が問題文中に書いていたり、設問で「監査手続を述べよ」と問われていたりしているので、それを参考にします。
| 項番 | 監査要点 | 監查手続 |
|---|---|---|
| 1 |
B 社通販課長は,業務委託先に送付するテストデータがマスク処理されていることを確認しているか。 |
データ依頼書の写しを閲覧し,B 社通販課長の確認印が押されていることを確認する。 |
| 2 |
空欄
|
受領書ファイルに保管されたデータ依頼書の写しと, P 社保守業務担当課長の確認印が押された受領書を照合し,テストデータ番号が一致していることを確認する。 |
| 3 |
B 社システム部は,業務委託先における情報セキュリティ教育の実施状況を適切に確認しているか。 |
P 社から提出された情報セキュリティ確認書を閲覧し,B 社通販課長の確認印が押されていることを確認する。 |
| 4 |
B 社システム部は,業務委託先を通じて,再委託先の情報セキュリティ管理状況を適切に確認しているか。 |
P 社から提出された情報セキュリティ確認書に,再委託先からの情報セキュリティ確認書が添付されていることを確認する。次に,再委託先から提出された情報セキュリティ確認書に, P 社保守業務担当課長の確認印が押されていることを確認する。 |
こういう事例を見れば、監査手続の表現や“監査証拠”(項番1の「データ依頼書の写し」など)、“監査要点”がどういうものなのかがわかります。
また、午後Ⅱ論述式試験では、設問アや設問イで「“監査要点”や“監査証拠”を含めて解答せよ」などと明確に書いていなくても、監査手続について書くときには“監査要点”や“監査証拠”を含めた方が良いのですが、そういうことの再確認もできると思います。
以上のようなことを意識しながら、まずは午後Ⅰの問題文を活用して、“監査手続の表現”を確立していきましょう。
そうすれば、午後Ⅰ対策も進みますし、午後Ⅱ対策も進みます。
Check-2. “リスク”と“コントロール”の表現も確立していますか?
“監査手続”の表現を固めたら、続いて、その監査手続を回答する “根拠” になる、 “リスク” と “コントロール”についての表現を固めていきましょう。
今度は、午後Ⅱの過去問題を使います。
通常、システム監査技術者試験の午後Ⅱ論述試験のうち、設問イや設問ウで“監査手続”が問われている問題は、ザックリ言うと次のような構成になっています。
- 実施したいことや目標
- それに対するリスクとリスク要因
- 2. に対するコントロール(監査人の考え or 実施しているコントロール)
- 3. に対する確認(監査手続)
しかし、上記の全ての要素が設問アや設問イで問われているわけではありません。“リスク”について問われていなかったり、“コントロール”が問われていなかったりすることもあるわけです。
では、問われていなければ書かなくてもいいのでしょうか?
そんなことはありません。話の展開から必要な時もあります。
したがって、問題文と設問を読む時に、上記の 1. ~ 4. を(設問ア、イ、ウの)書く必要があるのかをその都度判断し、必要な場合はどこ(設問アや設問イの中の場所)に書けと指示されているのかを考えて、対応するようにしましょう。
そうすれば、出題者の考える論旨展開にあった論文が書けるでしょう。
なお、システム監査人は第三者の立場なので、当時者が認識している“リスク”や実施している“コントロール”に加えて、監査人が必要だと考えるものがあるということも意識しておきましょう。設問を読む時には、どちらが問われているのかを“正確”に読み取って、それに対して“正確”に述べることができるようにしておきましょう。
Check-3. “監査手続”以外の問題についても解答をシミュレーションしておく
最後になりますが、時間があれば…念のため “監査手続” 以外の問題にも目を通しておきましょう。
あくまでも Check-1. と Check-2. を優先した上で、ある程度メドが立った後で構いません。
監査手続以外の問題を読んで、頭の中でシミュレーションしておけば万全です。
これから開始する人、これまでに準備ができている人
ということで、これから試験対策を開始する人は、上記のCheck-1. ~3. を進めていきましょう。
システム監査技術者試験の午後Ⅱ論述試験は、過去問題を見る限り、おおよそ問われることは“監査手続”だと決まっています。
もちろん監査対象は問題によって異なりますが、そこは当事者として考えればイメージできないこともありません。したがって、監査特有の表現を会得すれば合格できる可能性は出てきます。
なので、自分の頭の中にあるイメージを、どうすれば監査特有の表現で伝えることができるのか、意識しておきましょう。
他方、これまでしっかりと準備できている人は、本番当日までに、準備した情報を用いて過去問題に沿う形で文章の “部品” を準備していきましょう。
読み込んだ過去問題に対して、200~400字の文章で用意しておくことで、“今から試験対策を始める受験生”を引き離すことができるでしょう。
早くから始めたという優位性を最大限に活かすことが、早くから準備をしてきた受験生の取るべき戦略になります。
label 関連タグ『定額制』
高度試験対策研修 KOUDO 初公開!
定額制だから、どの区分でも何名でも受け放題!!
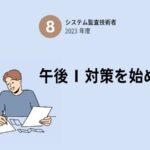

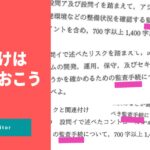
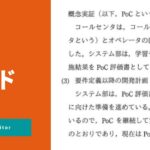



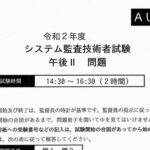

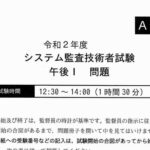



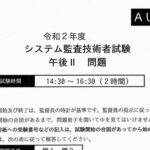

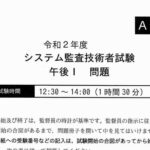
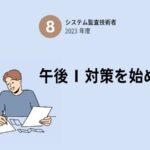




- 略歴
- 株式会社エムズネット代表。
大阪を主要拠点に活動するIT コンサルタント。 本業のかたわら、大手 SI 企業の SE に対して、資格取得講座や階層教育を担当している。高度区分において脅威の合格率を誇る。 - 保有資格
-
- 情報処理技術者試験全区分制覇(累計 32 区分,内高度系 25 区分)
- ITコーディネータ
- 中小企業診断士
- 技術士(経営工学)
- 販売士 1 級
- JAPAN MENSA 会員
オフィシャルブログ 「自分らしい働き方」Powered by Ameba