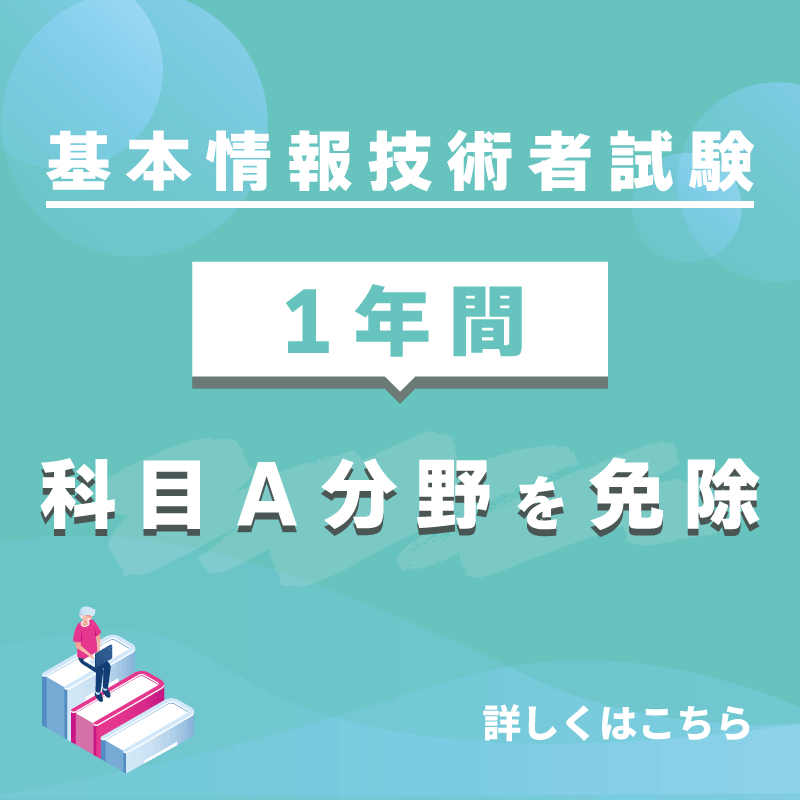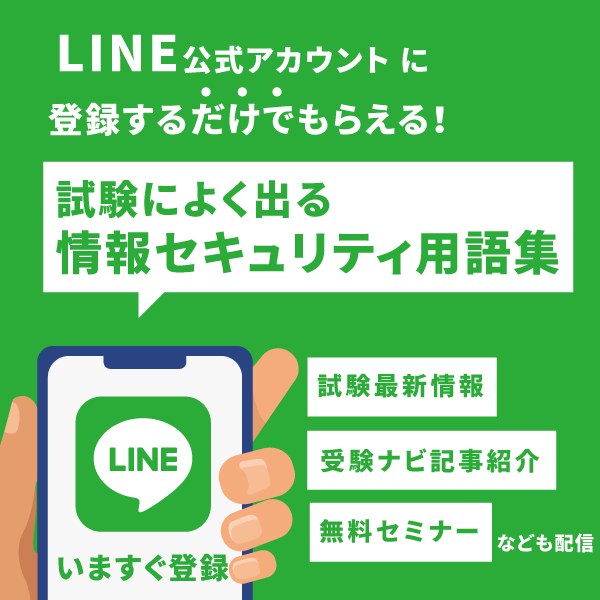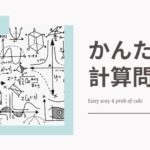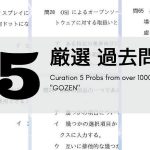「過去問題は何年分まで解くべき?」「何を中心に学習すべき?」|基本情報お悩み相談室

この連載は、基本情報技術者試験の受験者を対象としたものです。
毎回2つずつ、受験者が抱えているお悩みに、講師歴20有余年の私がお答えします。
お悩みの中には、技術的なものもあれば、精神的なものもあります。
どちらも解決して、スッキリした気分で受験勉強をしましょう。

矢沢 久雄
IT技術を楽しく・分かりやすく教える“自称ソフトウェア芸人”。
大手電機メーカーでPCの製造、ソフトハウスでプログラマを経験。独立後、現在はアプリケーションの開発と販売に従事。その傍ら、書籍・雑誌の執筆、またセミナー講師として活躍。軽快な口調で、知識0ベースのITエンジニアや一般書店フェアなどの一般的なPCユーザの講習ではダントツの評価。大手電機メーカーでPCの製造、ソフトハウスでプログラマを経験。独立後、現在はアプリケーションの開発と販売に従事。その傍ら、書籍・雑誌の執筆、またセミナー講師として活躍。軽快な口調で、知識0ベースのITエンジニアや一般書店フェアなどの一般的なPCユーザの講習ではダントツの評価。
■主な著書
「プログラムはなぜ動くのか(日経BP社)」「でるとこだけ!基本情報技術者(翔泳社)」など多数
【お悩み1】
過去問題は何年分までさかのぼるのが良いのでしょうか?
現行制度の基本情報技術者試験は、科目Aと科目Bから構成されています。
科目Aの内容は、問題数が少なくなったこと以外は、旧制度の午前試験と同じです。
したがって、科目Aの学習題材となるのは、現行制度の過去問題(公開問題とサンプル問題)と旧制度の午前試験の過去問題です。
科目Bの内容は、旧制度の午後試験とまったく異なります。
したがって、科目Bの学習題材となるのは、現行制度の過去問題(公開問題とサンプル問題)だけです。
科目Bの過去問題は、数が少ないので、全部学習してください。
科目Aの過去問題は、この記事の執筆時点で、令和6年度から平成21年度春期まで、膨大な数があるので、全部学習するわけにはいかないでしょう。「それでは、科目Aの過去問題を、どれくらい解けばよいのか?」というのが、このお悩みですね。
答えは「何年分や何問ではなく、できるようになるまで」です。
1000点満点で600点以上が合格なのですから、「60%以上できる!」という自信を持てるようになるまで学習してください。
あるスポーツ選手が「何時間練習するとか、何回練習するではなく、できるようになるまで練習しないと、できるようにならない」と言っていました。
これは、試験の学習でも同じです。
とは言え、どのくらい学習すればよいか、どのように学習すればよいか、ということに目安を示さないと、回答になりませんね。
令和6年度の公開問題を見ると、全20問中(実際の科目Aの問題数は60問ですが、公開問題は20問だけです)の13問(65%)が過去問題の再利用であり、最も古いものが平成21年度秋期で、最も新しいものが平成30年度秋期です。
幅広い年度の過去問題が再利用されていて、特定の年度の過去問題の再利用が多いという傾向はありません。
したがって、新しい過去問題から順にさかのぼって学習する必要も、特定の年度に絞る必要もありません。
年度にこだわらずに、苦手分野の過去問題を重点的に学習してください。
「苦手分野の過去問題を重点的に学習してくださいと言われても、苦手分野がわからない」という人もいるでしょう。
苦手分野を知るためにお勧めの方法は、何らかの教材を入手して(既に教材をお持ちならそれを使って)、分野ごとに分けられた章にある問題を解くことです。
60%以上正解できなかった分野が苦手分野だと判断できます。
苦手分野がわかったら、当然ですが、その分野を教材で学習してください。
そうして、知識を得ることができたら、その分野の過去問題を数多く解いてください。
インターネットを「基本情報技術者試験 過去問題」で検索すると、分野ごとに過去問題と解説を掲載しているWebページがいくつか見つかると思いますので、それらを利用するとよいでしょう。
苦手分野は、いくつかあると思います。
「ある程度、苦手分野を克服できた!」という自信を持てたら、どの年度でもかまわないので、試験1回分の過去問題を解いてください。
試験1回分の過去問題は、試験を実施しているIPA(情報処理推進機構)のWebページから入手するとよいでしょう。
解説はありませんが、問題と解答を入手できます。
60%以上正解できたら、目標達成です。
もしもダメだったら、できなかった問題を、できるようになるまで練習してください。
そして、また1回分の過去問題にチャレンジします。
これを、60%以上正解できるようになるまで繰り返すのです。
私の講師経験上、「IT企業の新人さんに、試験10回分の過去問題を解かせたところ、ほぼ全員が合格した」という事例がありますので、最大で10回分が目安になるでしょう。
「ええっ、10回分もやるの!」と思うかもしれませんが、最大で10回分です。
【お悩み2】
膨大な試験範囲に圧倒されています。何を中心に学習すべきですか?
IPA(情報処理推進機構)のWebページで、基本情報技術者試験のシラバスが公開されています。
これは、試験に出題される知識と技能の細目を分野ごとに詳しく示した資料です。
この記事の執筆時点で最新のシラバスVer.9.1は、全部で114ページもあります。
これを見ると、膨大な試験範囲に圧倒されてしまうでしょう。
ただし、シラバスの中には、試験に出たことがない項目もあれば、一般常識で理解できる項目もあります。
したがって「何を中心に学習すべきか?」というお悩みへの回答は、「試験によく出る項目と、一般常識では理解できない項目を中心に学習する」です。
これらを効果的かつ効果的に学習できる教材は、市販の試験対策本です。試験対策本には、試験によく出る項目と、一般常識では理解できない項目がまとめらているからです。
本屋さんに行くと、膨大な種類の教材がありますので、それらの中から自分に合った教材を選んでください。
自分に合った教材を選ぶコツは、教材の索引を見て、自分の知らない言葉を取り上げているページの説明を読むことです。
説明の内容がわかれば、その教材は自分に合っています。
人によって、合っている教材は違いますので、インターネット書店の書評にまどわされずに、実際に自分の目で確認して選んでください。
多くの教材が500ページくらいあるので、そのボリュームに圧倒されてしまうかもしれません。
そこで、とっておきの秘策があります。
これは、私が講師を始めたばかりの頃に、大ベテランの先輩講師から教わった秘策です。
本というものは、章ごとに小冊子になっていて、背表紙の部分でノリ付けされています。
そのため、ハサミやカッターナイフを使って、章の区切りごとに切り離すことができます。
ケガをしないように十分に注意して小冊子に分けたら、自宅で学習する場合も、外出先で学習する場合も、「今日は、この小冊子を学習しよう」と感じたものを選んでください。
500ページの分厚い本ではなく、十数ページくらいの薄い小冊子ですから、圧倒されることはないでしょう。
気軽に選べると思います。
そして、ここが最大のポイントなのですが、「この小冊子の内容は十分にわかった」と感じたら、その小冊子を別の場所に移してください。
こうすることで、後どのくらい学習すればよいかが、目に見えて減っていきます。
やる気がわいてきて、どんどん学習を続けられるはずです。
ぜひ、やってみてください。
プログラミングの経験がない人は、プログラミングの学習にも力を入れてください。
試験の出題テーマは、「アルゴリズムとプログラミング」なので、何らかのプログラミング言語の入門書と、そのプログラミング言語でアルゴリズムとデータ構造を学べる書籍を入手してください。
プログラミングの学習は、実習あるのみですから、それぞれの書籍に示されたすべてのサンプルプログラムを、実際に作って動作確認してください。
これには、かなりの時間がかかりますが、とにかくやるしかないです。
先ほど説明した市販の試験対策本と、並行して学習を進めるとよいでしょう。
今回は、「過去問題は何年分まで?」「何を中心に学習すべき?」というお悩みにお答えしました。
同じお悩みをお持ちの皆さんの参考になれば幸いです。
それでは、またお会いしましょう!
SEプラス公式YouTubeのIT教育チャンネルでも、矢沢のお悩み相談室シリーズを公開しています!
おすすめの学習方法・教材の選び方、用語の覚え方など語っているシリーズ1の動画はこちらから!
これから試験勉強をはじめる方は、ぜひ動画もご確認ください!
免除試験を受けた 74.9% の方が、科目A免除資格を得ています。
※独習ゼミは、受験ナビ運営のSEプラスによる試験対策eラーニングです。

『プログラムはなぜ動くのか』(日経BP)が大ベストセラー
IT技術を楽しく・分かりやすく教える“自称ソフトウェア芸人”
大手電気メーカーでPCの製造、ソフトハウスでプログラマを経験。独立後、現在はアプリケーションの開発と販売に従事。その傍ら、書籍・雑誌の執筆、またセミナー講師として活躍。軽快な口調で、知識0ベースのITエンジニアや一般書店フェアなどの一般的なPCユーザの講習ではダントツの評価。
お客様の満足を何よりも大切にし、わかりやすい、のせるのが上手い自称ソフトウェア芸人。
主な著作物
- 「プログラムはなぜ動くのか」(日経BP)
- 「コンピュータはなぜ動くのか」(日経BP)
- 「出るとこだけ! 基本情報技術者」 (翔泳社)
- 「ベテランが丁寧に教えてくれる ハードウェアの知識と実務」(翔泳社)
- 「ifとelseの思考術」(ソフトバンククリエイティブ) など多数