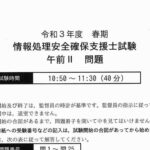午後Ⅱ問題対策 論文の書き方~ ITストラテジスト・システム監査技術者・プロジェクトマネージャ・システムアーキテクト・ITサービスマネージャ共通
3週間前点検~午後Ⅱ共通~
経験者として“経験”したことの強みをアピールできていますか?
午後Ⅱ論述試験は,一般的な学術論文のように何かしらの研究テーマで発見した規則性や法則を述べるのではなく,その真逆だと考えてもらえればわかりやすいと思います。
そうした規則性や法則などの“あるべき姿”は問題文に書かれていて,それを知っているかどうか?それを使った経験があるかどうか?が問われています。
だから,採用面接や口述試験に似ています。
信用も信頼もされていない,すなわちあなたのことを全く知らない第三者が,その文面だけを見て,経験していることを書いているかどうかを評価するわけです。
したがって,経験者の方が有利であることは間違いなく,経験者は自分の強みをアピールできれば合格に近づくというわけです。
経験のアピール方法
しかし,せっかく題材(試験問題)にマッチする素晴らしい経験をしているのに,それを表現できずに合格論文にならないというケースがかなりあります。採点者は,どこの誰が書いた論文なのかを知りません。したがって,(当たり前ですが)その論文に書かれている内容だけで評価するので,仮に経験者であったとしても,それを客観的かつ具体的に表現できていなければ,経験者であるということ,経験しているということは伝わらないのです。
ここで,経験をしっかりとアピールするベストな表現方法が,“客観的表現”と“具体的表現”だということは強く意識しておきましょう。経験したという事実のアピールは「私は,大企業のITサービスを,部下を200人したがえて日々奮闘している」的な表現だけでは不十分です。そうではなく,素晴らしい経験をした自分にしか出せない“具体的”なことを初対面の第三者に伝わるように“客観的”に表現することが必要です。
そうした“客観的”かつ“具体的”な表現に最も適しているのが“数値”での表現です。特に,経験したことを,経験した人しか出せないという目的に適しているのは,“%”などの比率ではなく実数。
問題文や設問で「定量的に…」という感じで,明示的に求められていない限り「必ずしも数値の表現は必要ではありません。求められている場合,%でも構いません。しかし,経験者が数値を出そうと思ったら出せるのに,出さないのはもったいない…そういう感じで考えておいてもらえるといいでしょう。
それに“数値”を出す表現を意識することで,具体性,客観性だけではなく一貫性なども意識することになるので,自ずと合格に必要な表現(ここで“国語力”と言っているもの)になってくるというメリットもあります。経験者はぜひ,意識することをお勧めします。
経験したことに無理やり合わせない
それともう1点,今度は逆に“経験者”が注意しなければいけない点も説明しておきましょう。
それは,いくら問題文と自分の経験が似ているからと言って,無理やり自分の経験に合わせようとしないことです。
このケース,論文添削をしていても一番多いケースです。
午後Ⅱ論述試験は,かなり細かい状況設定になっています。そのため,その試験区分の立場の人でも,問題によっては“未経験”のケースが少なくないのです。
「いや,俺は30年もやってきているから…」
と経験豊富なベテランの方でも,それは同じです。というか,そういうベテランの受験生の方が一見すると“似たような経験”をたくさん持っているので,それを書いてしまって少し違うB評価になったりします。
重要なのは,全ての問題を経験に引きずられないようにフラットに読むと言うこと。変な先入観を持たないことです。最初から「自分のどの経験だろう?」ではなく,どんなベテランの方でも「経験していないだろう」という視点で入っていくのがベストです。そうして,「あれ?」,「あれ?」…「ひょっとして,あの時のあの経験が…」という感じで,問題文を正確に読み込んで,自分の経験を当てはめていく方が安全です。
label 関連タグ『定額制』
高度試験対策研修 KOUDO 初公開!
定額制だから、どの区分でも何名でも受け放題!!

- 略歴
- 株式会社エムズネット代表。
大阪を主要拠点に活動するIT コンサルタント。 本業のかたわら、大手 SI 企業の SE に対して、資格取得講座や階層教育を担当している。高度区分において脅威の合格率を誇る。 - 保有資格
-
- 情報処理技術者試験全区分制覇(累計 32 区分,内高度系 25 区分)
- ITコーディネータ
- 中小企業診断士
- 技術士(経営工学)
- 販売士 1 級
- JAPAN MENSA 会員
オフィシャルブログ 「自分らしい働き方」Powered by Ameba