オンライン研修は単なるライブ中継に非ず!|「教えない研修」特集 2
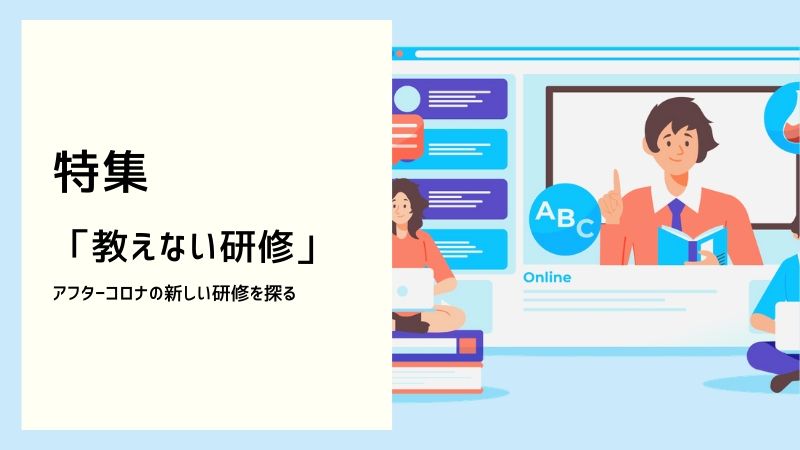
当初、オンサイト研修をオンラインで実施することで、学習効果が下がるのではないか?と懸念をしていましたが、いざ実施してみると良し悪しはあるものの、その心配は杞憂に終わりました。
オンライン研修では質問が活発!?
その懸念の中でも、特に、
「受講者がなかなか質問できないのではないか?」
「講師が近くでサポートができない点も学習効果に影響があるのではないか?」
と心配をしていましたが、フタを開けてみると講師が説明をしている間でもテキストチャットで質問できるため、質疑応答時間まで質問を溜めておく必要がなく、忘れることもありません。
またオンサイト研修でよくある、多少の勇気を振り絞って質疑応答時間に挙手して、ということもオンライン研修では必要ないので、特に質問は活発になったとさえ感じます。
私が勤める会社の新入社員技術研修サービスでは、主にソフトウェア・エンジニアになる方を対象に Java というプログラミング言語を中心に 3 ヶ月間学ぶ内容です。
通常ですと、 1 クラスあたり 20 〜 30 名に対し、講師はカリキュラムの内容を説明するメイン講師 1 名と、質問などメイン講師だけではサポートが足りない部分を補助するサブ講師 1 名がいます。
この研修を緊急事態宣言下は、 Google Meet と Slack を用いて完全にオンラインで実施しました。
メイン講師の説明は Google Meet でライブ配信し、受講者側は音声を切って、顔の映像は流してもらいました(助成金の受給条件の兼ね合いもあります)。
質問は基本的には Slack を使って、全員が見えるチャンネルに投稿してもらいました。
オンライン研修のメリット・デメリット
学習効果という観点で、新入社員技術研修のオンライン化のメリット・デメリットを備忘録も兼ねてまとめてみます。
-
メリット
- 質問しやすい(説明中にも手を挙げることなく、テキストチャットで質問できる)
- 正確な理解や用語の使い方などが伸びる(講師に伝わるような文章にする必要があるため)
- 質問が聞き取れない、さっきの質問なんだっけ?ということがない(テキストチャットに回答も残るため)
- 居眠りが減る(取り残されたときなどに自身でカバーしないといけないため?)
- タイピング速度が上達する(タイピングする機会が多いため)
- 補講の参加率が高い(通勤時間がないため)
- 復習がしやすい(研修で使っているPCが常に手元にあるため)
-
デメリット
- インターネット環境が貧弱な受講者は通信がときどき切れてしまうことがある
- 机・椅子などの学習環境が整っていないと集中できない
- PCトラブルが発生したときに、即時のサポートが得られない(PC交換が必要な場面も)
- タイピングが遅い人は質問しにくい
- 周囲の受講者の理解度や進捗が分かりにくい、自身の状況がつかめず不安になる(危機感も希薄)
- 理解度の格差が大きい(積極的な人とそうでない人によって理解度の差が開きやすい)
- 自ら声を上げない限りは、サポートが得られない(受講者のディスプレイを共有していないため)
上記のように、デメリットもありますが、オンライン研修だからといってオンサイト研修に比べて劣るということはないことが実施してみてわかりました。
また、デメリットの部分はファシリティ面でカバーできるところは改善していければと思います。
一方で、受講者自身の姿勢にも影響される部分があることもわかりました。言ってしまうと、主体性が高い方であれば良いのですが、逆に主体性が低い方ですとサポートが得にくく、置いていかれてしまう傾向があるということです。
オンライン研修でクラスの主体性が上がったという講師が 7 割!
その主体性に関して新入社員研修を担当した講師にアンケートしたところ、オンライン研修の方が高いというクラスが約 7 割、去年と変わらないというクラスが約 3 割ありました。
調査できた母数は少ないものの、多くのクラスでは主体性が高まったというこの結果は驚きの数字でした。
これは私が以前から思っていたのですが、学校のように講師が前に立って、受講者がスクール形式に座る研修は、受け身を助長するのではないかということです。
前に立つ講師が進行をコントロールするため、受講者にイニシアチブがなく、流れに身を任せるしかないスタイルだからです。スクール型で先生に教えられるスタイルを学生時代に長年に渡って受けてきた私たちは、スクール型だと無意識のうちに受け身になってしまうのかもしれません。
オンサイト研修において講師が受講者に説明する際には、多くの受講者がホワイトボードやスクリーンを見る観点からスクール型が適していて、仕方がない部分もあります。
また、例えば手が止まっている受講者がいれば講師が声をかけたり、プログラムをコーディングしている途中で間違っている様子が後ろから見えれば講師が手を差し伸べたりといったことができます。
対するオンライン研修は、講師からすると受講者の様子(理解度など)が把握しにくい・サポートしにくいという面がありますが、反面、受講者からするとサポートが得られにくい、物理的に助けてもらえる環境ではないという面があります。
特に受講者には主体性を高くもって研修に臨んでいただく必要があり、言い方を変えると、待っていても助けてくれない状況であるため、主体性を高く持たざるを得ないということでもあると思います。
そこで、次の特集では、講師すらいない研修、広がりを見せる「教えない」研修とはどんなものか、ご紹介します。
特集3
費用対効果、時間対効果でも有効な「教えない」研修

株式会社クロノス 関東事業部 ゼネラルマネージャ
「研修の受講者だけではなく、受講された方のお客様にまで、広く多くの笑顔を作る」をモットーにIT企業の技術研修やPM研修などを担当。
最近はAIの研修やセミナーにも多数登壇・講演の実績がある。
- 著作
- [記事]AI人材育成(トレタン)
- [記事]AIでシステム開発はこう変わる(AINOW)
- [書籍]Seasar2によるWebアプリケーションスーパーサンプル(SBクリエイティブ)
- [雑誌]eclipseパーフェクトマニュアル(技術評論社)
- [記事]Webの上のポジョをシームレスにつなぐJBoss Seam(@IT)
- [記事]IT人材の必要性と効果的な採用方法(@人事)
- など