IT研修 制度インタビュー|コアテック ~制度よりも「文化」としての育成を

IT研修制度は、よくあるヒューマンスキルや階層別研修とは異なり、情報技術 ( IT ) を専門にするので、なかなか構築が難しく、また移り変わりも速いため、運用も難しいものです。
そこで、IT研修制度がどのようなものか、実際に企業様にお邪魔してインタビューして、その制度構築や運用のコツなどを伺っています。
第 8 弾の企業様は、 株式会社コアテック さまです。

| IT エンジニア人数 51 名 |
| 2009 年設立 |
| グループ企業を中心とした Web サイト / アプリケーションの受託開発 |
Web インテグレーション事業部 部長
入社 6 年目。ランキングサイト、求人サイト等の開発チームを統括。趣味はアイドル鑑賞。
Web インテグレーション事業部 部長
入社 3 年目。求人サイト、店舗検索サイト等の開発チームを統括。趣味はテニス。自衛隊出身。
自走力がある人を育てるには ?
- これまでの研修制度インタビューでは、新しい技術もレガシーな技術も扱う企業様が多かったのですが、コアテックさんは Web システムが専門です。
まずは社内の技術スタックを教えて頂いてもよろしいでしょうか?
- Web 技術とクラウド 100% な技術スタックですね~。
私自身はあまり、そういった企業様の研修制度を伺ったことがないのですが、どんな制度があるのでしょうか?
なので、実は、 会社としてカチッとした研修制度はない んですよ。。
- ( 😨 😨 えっ ) . . . えーっと、では、チームごとにはどんな研修があるのでしょうか ?
- やっていまし「た」ということは . . .
- な、なるほど。。 ( ヤバいヤバい、取材が終わってしまう 😱😱😱 )
で、では、チームで共通の育成する人物像、指針のようなものはございますでしょうか?
- なるほど、なるほど!! ( ホッ 😌 )
それはなかかな難しいゴールですが、自走力をつけるにあたって気をつけていることは、どんなものがありますか?
メンバーが考えたことを、なぜそうやったのか、しっかり聞き取るようにして、決して、上からの意見で潰されないように、かなり気をつけていますね。
例えば、仕様や設計とかにムラがあったして、それに気付いて質問する、疑問点を出すといった行動が出来るようにと考えています。
- 「自分で考えること」ですか。なかなか私には耳が痛い。。
コアテックさんの場合、その習慣をどのようにつけさせようとしてらっしゃるのですか?
その興味や適性を、日頃の業務やコミュニケーション、面談などから可能な限りキャッチして、 できるだけ、本人が興味を持って取り組めるようにしています。
まずは興味を持てないと、「自分で考える」という積極的なアクションに繋がらないので。
- なるほど。確かに、興味のあるものは放っておいても、情報収集したり積極的に取り組みますね。( 私の場合、「阪神 🐯」とかなんですが . . . )
「ノリ」がとっても大事
- 各自が別々のことに取り組むと、スキルの評価がとてもむずかしいように思います。どのようにされてらっしゃいますか?
意図としては、受託開発という性質上、本人の持っているスキルと 100% マッチする案件に入るわけではなく、例えば、データベースで高度な技術を持っていたとしても、必ずしもその技術を活かせる案件にアサインされるとは限らないので、本人が持っているスキルをしっかりと把握・評価したい、という思いで使っています。
- なるほどですねぇ~。( ト、トラック ? いすずの話?? 🚛💨 )
その トラック? というものはどういうツールなんでしょうか ? どこかで名前を聞いた覚えがあるような . . . ( ゴニョゴニョ )
track は単体テスト採点が導入されており、可読性や実行速度をみるソースコードレビュー機能があります。
また課題によって、セキュリティ、データベース、アルゴリズムなどさまざま角度からスキルを測ることができます。その中から Web 開発にフィットした問題を選択して出題しています。
それで明確に点数がでるので、それをもってある程度、評価を定量化しています。
なので、メンバーは定量的なもの、定性的なもの、あるいはそのいずれも、など各々で目標を立てやすいと思います。
ただ、これも完成と思っているわけではなく、より確度と納得性、透明性の高い評価方式を追求し続けていくつもりです。
- なるほど~、そういったツールなどでスキルを共通評価すれば、確かにメンバーの興味がさまざまでも吸収できそうですね。( t r a c k 。メモメモ。。)
さらに進むと、そういった定量的に測れるものとして、社内 ISUCON のようなコンテスト形式も今後、良いかもしれませんね
えーっと、ISUCON といえば、尾下さん出てませんでした?
それに、あれを準備するのは、めちゃくちゃ大変ですよ。(笑)
そういった社内コンテストはやっていませんが、 社内勉強会や LT 大会のようなもの は、わりと長い間やっていますね。
- あら、そうなんですね! その社内勉強会や LT 大会は何か施策として取り組んでいるのですか ?
- めちゃ、いいネタじゃないですか!! 早く言ってくださいよ~ (笑)
これもやっぱり 「ノリ」 です。(笑)
いま流行っていて、毎年夏に、豊洲にテントが張れて BBQ ができるアウトドア会場のようなものが出来るんですが、そのテントの中で “もくもく” 開発する、というものです。(笑)
そこでやるとチームワークがよくなると言われていて、ちょっとやってみたいですね。
- ちょっと絵面がシュールですね。 (笑) 青空の下、テントでもくもく会。
開発環境などはどうするんですか?
- なにか間違った AWS の使い方のような気がします。(笑)

ソフトな印象の、「ノリ」重視の尾下さん
みんながアウトプットすることで「育成」につながる文化
- 伺っていると、「育成」しているんですが、一般的な研修制度のようなものではない、そんな感じがしてきました
やっぱり「楽しそうだ」と思って集まって、それに刺激を受けてスキルアップに繋がったり、周りを巻き込んで輪が広がったりするほうがよいと思うんですよ。
いま、尾下がやっている Raspberry Pi ( ラズパイ ) のやつもそんな感じです。
- いいですね、いいですね !
なので、強制的に定期でやろう、といったものはありません。
- ちなみに、社内勉強会はどんなテーマで開催されているのですか?
始まったのは Docker が出てきたときぐらいからと認識していて、私が知っている範囲では AWS Fargate だったり、Vue.js だったり、あとは Xdebug を各エディタに導入するやり方とか、大きなものから、ちょっとした Hack のようなものまで、本当にさまざまです。
フロントエンド側が、バックエンドがいれた環境や API を学ぶものだったり、それとは逆に、バックエンド側がフロントエンドが入れた施策を学んだり、そういったものが開催されています。
フロントとバックは技術が違うので、そうすると余計なハレーションが起こりがちです。そこで、お互いの文化を学ぶ、というのが重要になるんですね。
- そんな「勉強会」文化なんですね !
社内 Wiki ではSEカレッジの受講したレポートなども書かれていますよ。
- へー、SEカレッジのレポートもあるんですか
- でたでた! グループワークだめですか (笑)
- その「アウトプット」にこだわるのには何か意図があるのですか?
- 「共有駆動」いいですね! そういった育成スタイル・文化が研修制度に近いのかも知れませんね
- ちなみに、そういった文化は意識して作り出したものなのでしょうか?
- もともと、そういった土台があったんですね

真面目でありながら、わりと「ノリ」好きな平田さん
「画面ポチ」の裏側をSEカレッジで学ぶ
- では、先ほどから挙がっている「SEカレッジ」について、SEカレッジには新しい技術を扱うコースもある一方、どちらかというと基礎的でレガシーなものが多いのですが、なぜ、導入されたのですか?
どういうことかというと、いまはフレームワークやライブラリ、ツールなどが発達しすぎていて、 DNS とかそういったことを知らずとも、AWS で画面ポチポチしていると、サーバーが立ち上がるんですよね。
- そうか、なるほど!
そこで、SEカレッジを受講すれば、その裏側にある、例えば TCP/IP など基礎になっているレガシーな技術を、社内用語ではなく、ちゃんと標準化された用語で学ぶことができるんです。
そうすると、何となくポチポチしていた項目も、セキュリティで必要だったのか、などわかるようになります。
これが、SEカレッジを入れた大きな理由の一つですね。
- 画面ポチポチの裏側は意識しないとわからないですよね
- なるほど、そういった目的でSEカレッジを受講頂いていたんですね。そのユースケース、勉強になります!
では、最後になにかメッセージがあれば、お願いします!
また、台湾とフィリピンに海外事業部もあり、台湾はオフショアを中心に据えつつ、現地受注もできる体制が整ってきました。一方のフィリピンは今まさに立ち上げ真っ最中なので、技術的なフェーズだけでなく、会社の成長フェーズも幅広く経験できます。
ご応募だけでなく、話を聞いてみたい、という方も歓迎していますので、お待ちしています!!
- 今日はありがとうございました !!
label SE カレッジの無料見学、資料請求などお問い合わせはこちらから!!
label SEカレッジを詳しく知りたいという方はこちらから !!
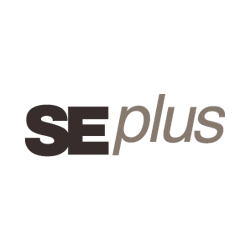
SEプラスにしかないコンテンツや、研修サービスの運営情報を発信しています。


DB も Amazon RDS ( Aurora 、MySQL ) や Amazon DynamoDB 、Redis などです。
IT エンジニアの人数構成としては、
ですね。