講師インタビュー 安井 力 「ゲームでわかるアジャイル!」

研修で「何を学ぶのか」も重要ですが、 「誰から学ぶのか」も重視される時代。SEプラスの研修で登壇する講師がどんなことを思いながらコースを実施しているのか、講師にインタビューしています。
今回は SE カレッジで開催するアジャイルのコースで、抜群の受講人数と満足度を誇る 安井 力 さんです!
アジャイル界隈では「やっとむ」さんというニックネームのほうが通りがいいかも知れませんね。 多くのアジャイル関連書籍に携わられ、国内外のカンファレンス、勉強会での数多くの登壇、さらには Fun / Done / Learn などパターンの開発もされています。
インタビューではアジャイルとの出会い、意外な英語の勉強方法に加えて、「アジャイルがわかるゲーム」も伺いました!
アジャイルを普及させるヒントが詰まった内容なので、ぜひご覧ください !!
アジャイルコーチとして 10 年以上、ソフトウェア開発の現場や組織がアジャイルになる支援を続けている。開発技術の紹介、チームビルディング、組織とプロセスの改善などに取り組む。
アナログゲームを用いたワークショップも提供している。「心理的安全性ゲーム」「宝探しアジャイルゲーム」「カンバンゲーム」など。
著書・訳書に『アジャイルな見積りと計画づくり』(毎日コミュニケーションズ 刊)『スクラム現場ガイド』(マイナビ出版 刊) 『テスト駆動 Python 』(翔泳社刊)『 Joy, Inc. 』(翔泳社刊) など。
プライベートでも最近購入した電動アシストバイクで 2 ~ 3 時間ツーリングしたり、 3 D プリンタで後戻り式 無料ロッカー用に 100 円玉が入るキーホルダを作るなど、精力的に活動。
インタビュアー: SEプラス 寺井 彩香
「エクストリームプログラミング」という名前に惹かれる
―― ちょっと本筋ではないことからの質問からですが、安井さんは本名の 安井力 さんより “やっとむ” さんと呼ばれることが多いですよね。 どのような由来があるのでしょうか?
―― まさしく「それだ!」ですね(笑)。 そんな やっとむ さんというと “アジャイル” が枕詞のようにつきますが、アジャイルとの出会いはどのようなものだったのでしょうか?
当時の私の仕事はプログラマだったので、 “エクストリームプログラミング” という名前そのものに興味が湧いたのです。 それで調べてみると面白そうで、有名な平鍋 健児 info 2さんが XP ユーザ会を始められていたので、それに参加するようになりました。
info 1XP (Extreme Programming) とは、コードレビューやテストファースト、 CI/CD 、ペアプログラミング、リファクタリングなど様々な開発ルールをまとめた総称で 1999 年に Kent Beck が解説書籍を発表
info 2日本で最初に XP を広めるなど、日本におけるオブジェクト指向開発とアジャイルの第一人者。 数々の書籍を執筆・翻訳し、国内外のカンファレンスで登壇。 日本のアジャイルを牽引する。 株式会社永和システムマネジメント 代表取締役社長。
その体験をもっと社内や社外にも広めたいと思って XP やアジャイルにのめりこんでいきました。
―― 当時、そんな現場が日本にあったとは驚きです! そのエクストリームプログラミングという名前から興味を持ったぐらいですから、プログラミングが好きだったのですね。 やっとむさんがプログラミングを始めたのはいつからだったのでしょうか?
―― 10 歳!?
私もそれでゲームを作ったり、ゲームキャラクタをつくるキャラクタエディタを作ったりしていました。
―― とても本格的ですね!
―― いえいえ、それでもそんな小さい頃に作れるものではないですよ。 それで、プログラミング好きが高じて、プログラミングが仕事になったと?
永和システムマネジメントは当時流行していたオブジェクト指向とアジャイル / XP 、さらに Ruby も開発で使おうと先進的に言っていたので、それに惹かれました。
「翻訳家」やっとむ を生んだ「多読」という英語学習方法
―― プログラミング好きにはとっても魅力的な会社ですね!
ちなみに、前職で Java をやっていたので、「 Java ができるならお客様向けの研修で講師やってみなよ」と言われて登壇したのが、講師になったきっかけでした。
―― アジャイル研修ではなく Java が講師デビューだったとは …
あとは永和システムマネジメントにいたときに書籍の翻訳も始めました。
―― やっとむさんの今の活動のほとんどは永和システムマネジメントさんから始まっているのですね。 翻訳するようになったきっかけはどのようなものだったのですか?
―― 自ら翻訳に応募されるということは、すでに英語にも自信があったのですね。 英語スキルはどのように磨かれたのですか?
―― 非常にユニークな授業ですね!
それが、期の途中で英語の先生が変わってしまい、仲間と一緒に酒井先生に「なんとかしてください」と直訴したところ、「研究室に通ってくれたら単位を出すよ」と言われて、それから入り浸り拍車がかかりました。 研究室では書籍だけでなく、映画やゲームで英語を学ぶという実験にも参加しました。
―― 視覚や聴覚も英語漬けですね。 その圧倒的な量が上達のコツだったのですね

「ゲームでわかるアジャイル!」とその理由
―― そんなユニークな授業の進め方に影響を受けられたのか、やっとむ さんの研修は講義だけでなく、アジャイルをテーマとした「アナログゲーム」のワークショップもありますよね
―― そんなにたくさん! どんなゲームがあるのでしょうか?
といったゲームがあります。
―― どれも面白そうですね! 少し紹介していただいてもよろしいでしょうか?
宝探しアジャイルゲームは、こんどはプロダクト全体の視点から、アジャイル開発を取り入れた会社がどのように仕事を進めるのか体験できます。 具体的には 3 ~ 5 チームにわかれ、それぞれが競合企業として、マーケットリサーチ、機能リリースなどをしてユーザの獲得数を競います。
―― アジャイルな会社の動きを体験するのは DX 化を進める企業にはうってつけですね! あと個人的に心理的安全性ゲームも気になります
―― 発言カードで強制的に否定的なことを発言させるのがゲームならではですね。 そもそものお話ですが、なぜ、「ゲーム」を題材にするようになったのでしょうか?
―― とても難しいテーマですね
―― アジャイルは知識よりも体験が効きやすい、ということですね
そこで短い時間でアジャイルを体験できるカタチを探して、生まれたのがゲームを使ったワークショップです。 ゲームを使うと研修のエンゲージを生み出しやすいだけでなく、例えば、カンバンゲームでは実際にチームでカンバンを使いますし、ゲームで起こる問題をみんなで解決するという体験もできます。
―― たしかに仕事で実践しやすそうですね! そのゲームの効果を伺いたいのですが、ワークショップ後の行動変容を追跡するのは難しいので、ワークショップ中のエピソードで何かございますか?
また自分が伝えたいことを飛び越えて、新しく気づくこともあります。
―― それはどんなことだったのでしょうか?
―― えっ、厳しいご意見のように聞こえますが …
―― ゲームでしっかり心理的安全性のポイントがわかったから言えるコメントだったのですね。 ゲーム形式のワークショップは様々な気づきを生みますね。 では、最後に受講者へのメッセージをお願いします!
ぜひ参加いただき、次の行動に移る何かを掴んでもらえれば、とってもうれしいですね。

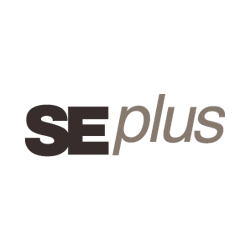
SEプラスにしかないコンテンツや、研修サービスの運営情報を発信しています。