講師インタビュー 植田 崇靖「電子回路から機械学習まで、学ぶことが楽しい!」
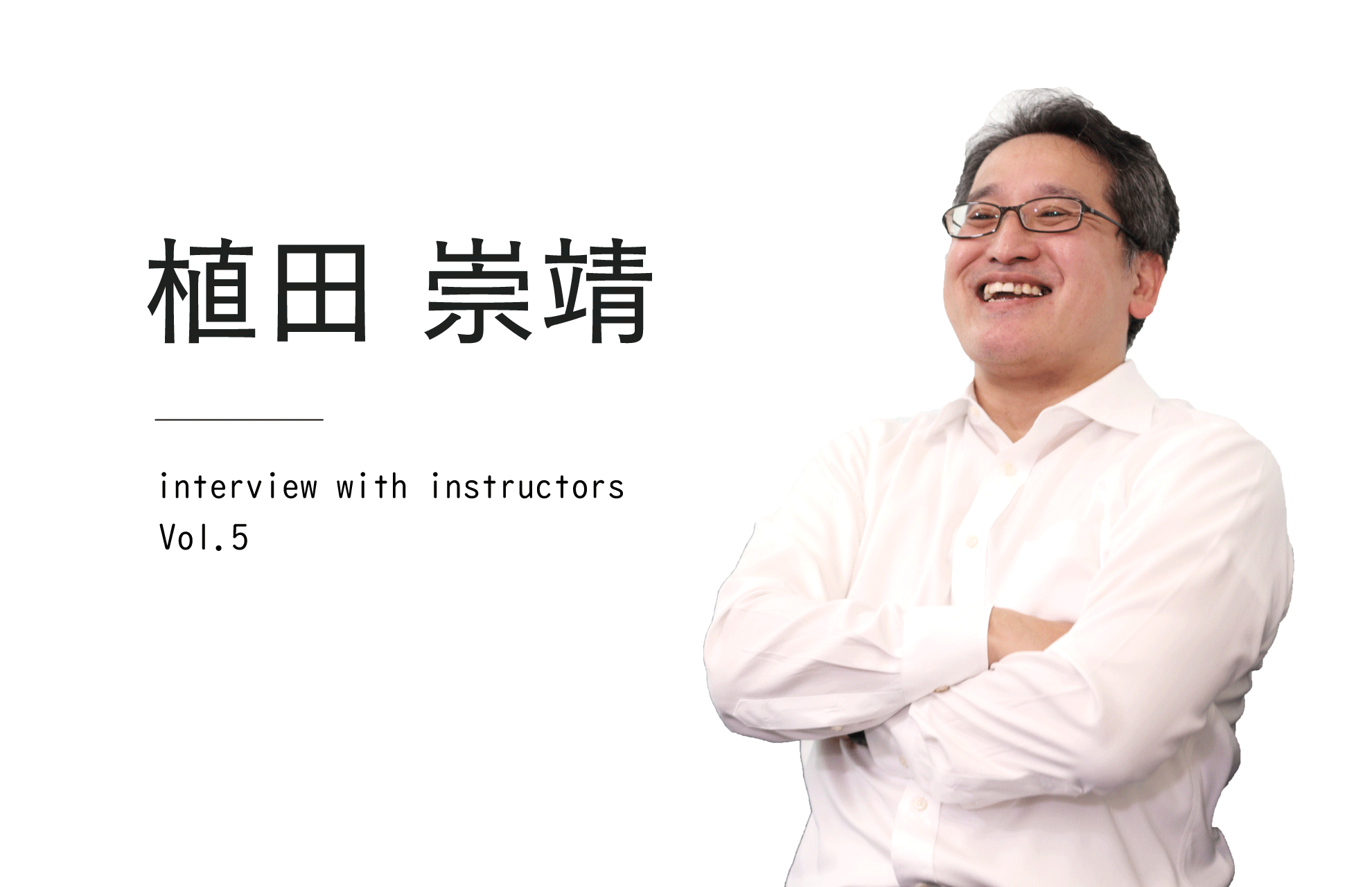
研修で「何を学ぶのか」も重要ですが、 「誰から学ぶのか」も重視される時代。SEプラスの研修で登壇する講師がどんなことを思いながらコースを実施しているのか、講師にインタビューしています。
今回は IoT に加えて、機械学習、 Web 技術、データベースなど、本当に沢山の分野で登壇する 植田 崇靖 さんです!
インタビューを通じて、植田さんの旺盛な「知的好奇心」が窺い知れたほか、 IoT ではどれだけフルスタックに技術が必要になるのか、また今の IoT の現状がわかりました! IoT のスキルを身につけるコツも伺いましたので、ぜひご覧ください !!
自動追尾台車「カルガモちゃん」を設計、製造するなど、機械設計、電気、電子回路設計および周辺知識に詳しい。現在では製品の性能向上のため主に機械学習を中心とした AI の研究も進め、センサーデバイスと組み合わせた IoT にも精通。そのほか Web アプリケーションフレームワークを使った EC サイトも構築するなど、まさしくフルタックな開発経験を持つ。
プライベートでは最近バイクを購入し、コロナが落ち着くのを見計らいながら、ツーリングを画策中。
インタビュアー: SEプラス 寺井 彩香
もくじ
初仕事は見たことも操作したこともないメインフレームを使った開発
―― 植田さんは IoT から Web 技術、機械学習と、世間相場のフルスタックより、さらに幅が広い分野でのご登壇が多いのですが、もともと IT 好きだったんですか?
非常に高額だったんですが、中学 2 年ぐらいでお年玉を貯めに貯めて念願の自分のパソコンを購入しました。ただ、それでお金は尽きてソフトは買えず、自分でプログラムを書くしかなかったんですね。それがプログラミングとの出会いで、それから趣味でプログラムを書くようになりました。
―― それで IT 系の会社に就職されたのですか?
いえ、大学の専攻も文系でしたので、一番最初に入った会社は IT ではなく製造業です。また配属された部門も工場の調達部門なので、全く IT が関係がありませんでした。プログラミングはあくまで趣味という感覚でしたね。
―― ということは、仕事で開発をするようになったのはもっと後ですか?
いえ、その会社で新入社員研修中に(笑)。
―― えっ(笑)
そういうリアクションになりますよね。今から考えると無茶苦茶なんですが、新人研修中に、ある資料制作の仕事を任されたのが、開発っぽいものの初仕事です。
―― … 研修とは? となりますね(笑)。どんな開発の仕事だったのですか?
配属された部門はいわゆる工場の管理部門で、メインフレームのコンピュータで毎月の生産や売上などを管理するシステムが稼働していました。
部門の上司から命じられた仕事というのが、そのシステムから毎月、売上データなどを取得し、毎月報告ファイルのエクセルで作成していたのですが、それを自動化するマクロを作ることだったんです。
―― それが新人たちに任されたと …
いえ。私の所属していた部門は情報処理の部門ではなかったですし、他の同期も同じ場所で研修は受けていたのですが私だけが他部署ということもあり、その場に直接の上司もおらず先輩もいませんでした。つまり、自分 1 人しかいなかったんです。
―― 研修も、初仕事も、部署もメチャクチャですね … 。そんな環境でどうされたんですか?
エクセルのマクロはまだいいんです。初めてでしたが、本も沢山あったので。
ただ、メインフレームばっかりは本当にわからない。それを研修先の先輩に言うと、電話帳ぐらいの分厚さのあるマニュアルを 3 冊を渡されて、「あとはよろしく」とのことでした。誰にも教えてもらえず。しかも納期は新人研修が終わるまでということで、 2 週間ぐらいしかありませんでした。
―― 失礼ですが、初仕事から壮絶にブラックですね …
なんとか頑張って、やり遂げました。まぁ、やりながらも初めて知ることばかりで、面白さもありました。
開発の仕事はそれで終わり、研修後は、本来の調達業務に戻りました。その工場では金属、樹脂、色々な素材を加工していたので、その部材を調達したり、値下げ交渉をしたりと、これも次から次に知らないことが出てくるので、楽しい仕事でしたね。
講師をすると学習が進む
電子回路・金属加工から IoT ・機械学習までフルタックに開発
―― なかなか今のような IT での開発が出てこないですね(笑)
ここからが本番です(笑)。
実家が工場をやっていて、と言っても町工場ですが、それを手伝うことになったので、新卒入社した会社を退職しました。
その実家の工場でモノ(機器など)を作っていたので、電子回路や金属加工をやるようになりました。
―― なるほど、メカや回路周りに詳しいのはそういった理由だったんですね
ただ、それだけでは先行きも不安でしたし、時代も今までは作っておしまいだったものが、インターネットにつなげて価値を出すように変化していることを感じたので、その変化に対応できるように 2011 年に新しく会社(合同会社 UESEI )を設立しました。
なので、最初から IoT をやろうと思っていたわけではなく、時代に合わせてやっていると、自然と IoT になっていました。
―― なるほど!モノづくりの進化に合わせていたら IoT になっていたんですね。では、新しく設立された会社でどんな開発をされていたのですか?
テレビなどでも取り上げられましたが、自動追尾する台車「カルガモちゃん」が代表的なものですかね。
―― Youtube で見たことがあります!
人のあとを自動で追尾する台車で、センサをつかって先行する人を認識し、モーターや走行制御などを行う仕組みです。機械学習、データ通信、サーバサイド、制御系のプログラムだけでなく、基板なども自作しているので、簡単ですが IoT らしい開発だったと思います。
―― 基板も自作とは、フルスタックにも程がありますね(笑)。現在ではどのような開発をされているのですか?
今のニーズは新しく IoT 対応の機器を作るのではなく、今までインターネットに繋がってなかった機器を繋げる案件が増えています。
最近手掛けた案件では、封筒の製造機(展開された紙を折り曲げて糊付け)が稼働しているのですが、今は製造した数は装置に見に行かないとわからないし、もちろんリアルタイムの生産数量や稼働状況などわからない。それをインターネットに繋げて、ほぼリアルタイムに製造枚数を把握するというものがありました。
そこで使ったシステムと技術は、簡単に表すとこんな感じです。

- カウント装置の信号を受け取る電子回路の作成: DCDC コンバータなどを使用
- マイコンでカウントして 5 分おきにデータ送信するプログラムの開発と電子回路の作成: C 言語で開発
- データストアとデータ表示するサーバプログラムの開発: PHP で開発
―― IoT は、やはり電子回路から組込みシステム、ネットワーク、サーバプログラム、データベース、本当に色々な技術を使いますね
講師になって勉強することが増えて楽しい!
―― 一方で、講師をするにようなったのは、どのようなキッカケがあったのでしょうか?
大阪市のあるイベントの一環で電子工作のワークショップが開催されるので、仕事仲間からその講師をやらないか、と声をかけられたのがキッカケです。もともと組込業界で私のようにフリーでやっている人間は当時は珍しく、また業界に講師をしたいという人も少ない、という背景もあって、声をかけられたのかなと思います。
―― はじめての講師で、抵抗はなかったのですか?
「 3 時間ぐらいで受講した人が達成感を感じてくれたら OK 」というカジュアルなオーダーだったことと、平日に参加無料なのでガチ勢はこないだろうと思ったので、ハードルは低かったですね。あとは座学でずっと話すスタイルではなく「モノを作る」ものだったことも良かったですね。
―― 実施してみていかがでしたか?
受講者も工作できて簡単ではありますが実際に動いたので雰囲気はよかったと思います。また大阪市の評価も良かったので、今でもチョコチョコ講師の仕事がきています。
―― それから講師の仕事が増えていったんですね
それから同じようなワークショップで登壇する機会が増えましたが、講師らしい「教える」という仕事が増えたのは、 2 年前に SEプラスから紹介された新人研修案件で2ヶ月ぐらい演習のサポート講師をやったことですね。
―― そうだったんですね!ありがとうございます
演習のサポートという立場でしたが、私からしたら本を書いているような有名な先生の研修を見る、いい機会になったので勉強できました。おかげさまで講師としての依頼を受けることが多くなりそれに応じて IoT だけでなく機械学習やデータベースや Web 技術など、分野を広げて行けていると思います。
―― 講師の仕事はいかがですか?
受講者からのアンケート結果で、満足している、理解できたという声が寄せられるようになったので、やりがいがありますね
あとは、人に伝えるというレベルは、開発で使うより、より一層理解できていないと出来ないので、それで勉強する機会が増えて楽しいですね。伝え方の勉強もできますし。
もともと、ものぐさだったので、今までは開発で使う部分を中心に勉強してきましたが、講師になると、それ以外の部分も勉強するようになりました。理解が薄いところ、例えば数学とかデータベースを勉強してみたり、新しいデバイスが出れば触ってみたり、と幅が広がっていて、とても楽しく勉強できています。
IoT は広大
―― 植田さんは IoT の研修での登壇が多いのですが、どんなことにこだわっているのですか?
SE カレッジで IoT の研修を実施すると、ハードウェアをはじめて学ぶという方も多く受講されます。このため、電気、電子のかなり初歩的な話から始めたり、実例を交えて研修するようにしています。
またコロナ前になりますが、ハードウェアを操作する演習のときは、ゆっくり時間を取っています。場合によってショートするなど危険なこともあるので。
―― 今は演習をどのようにしているのですか?
さすがに演習で使う実機を受講者に送れないので、今はカメラの前で、私が動かすデモをやっています。
そのときも、見て面白そうと思える題材を選んだり、始めやすそうと思ってもらえるように、工夫しています。それで「自分でもやってみよう、再現しよう」という人が増えて欲しいですね。特にハードウェアに興味を持つ人が最近は少なくなって来てますので。
―― IoT を学ぶコツはあるんでしょうか?
さっき私の開発実績でもお話したように、一口に「 IoT 」と言っても、とても幅が広いです。ハードウェアを作る人もいれば、そのハードウェアからサーバにデータを伝送する組み込みの部分のプログラムをする人もいれば、データを様々なデータベースに入れるサーバプログラムを書く人もいれば、その集まったデータを分析する人もいます。
本当に様々なので、すべて学ぼうとすると、とても大変です。このため、普段の業務で使う技術スタックから徐々に広げるのがオススメです。
その幅を広げようと思ったときに、参加しやすい研修を作っていますので、ぜひ受講いただきたいですね。
―― 今日はありがとうございました!
ありがとうございました。

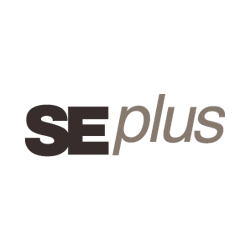
SEプラスにしかないコンテンツや、研修サービスの運営情報を発信しています。
中高生だったころ、年代でいうと 80 年代後半から 90 年代前半 のころにパソコンが流行っていました。 Windows 3.1 が出る前で PC 9800 シリーズが流行っていた頃です。