アパレル業界の DX 化とは?|SEカレッジ ウェビナーレポート
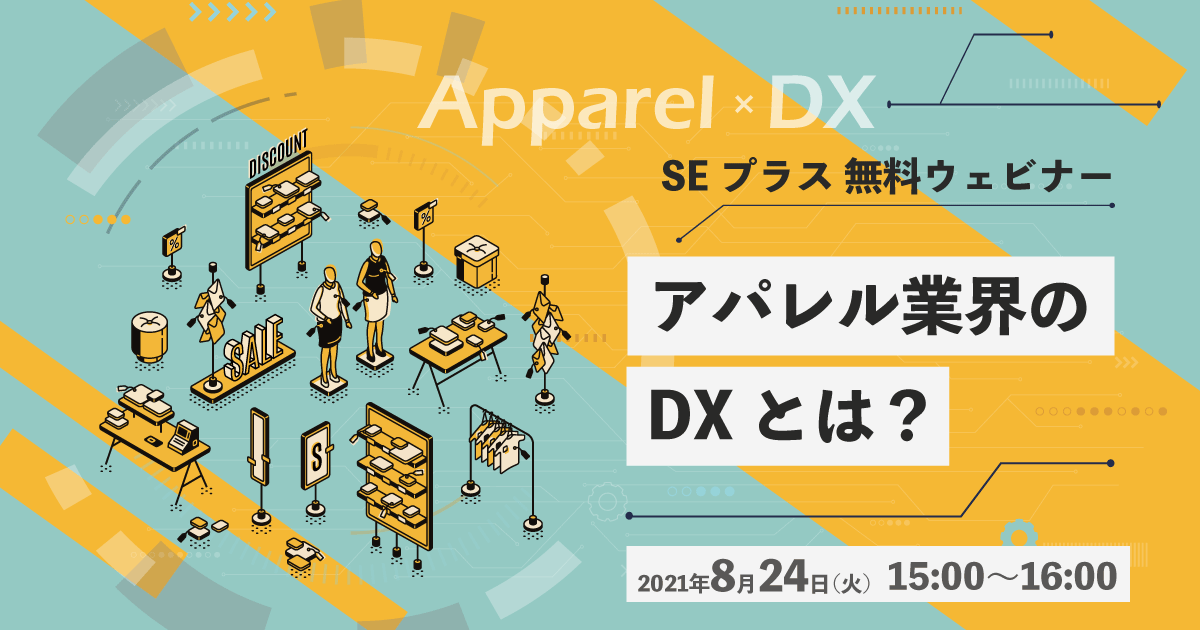
SE カレッジでは旬のテーマをもとに、 1 時間のウェビナーを毎月 1 回以上、開催しています。
今回のテーマは、 「アパレル業界の DX 化とは?」 です。
「お店で試着してから買う」という当たり前が見直され、レンタルからオンライン接客まで、いろいろなサービスが登場しています。そんなアパレル業界の DX の今と未来について、 天沼 聰 さんと 木下 貴博 さんをお招きし、お話を伺いました。
-hhh.jpg)
株式会社エアークローゼット 代表取締役社長 兼 CEO
1979 年生まれ、千葉県出身。高校時代をアイルランドで過ごし、英ロンドン大学コンピューター情報システム学科卒。 2003 年アビームコンサルティングに入社し、 IT ・戦略系のコンサルタントとして約 9 年間従事。 2011 年に楽天株式会社に転職し、 UI / UX に特化した Web のグローバルマネージャーを務めた後、「ワクワクが空気のようにあたりまえになる世界へ」をビジョンに、 2014 年 7 月に株式会社エアークローゼットを設立。日本で初めての普段着に特化した月額制ファッションレンタルサービス『 airCloset 』を立ち上げ、その後もパーソナルスタイリングを提供するサービスを中心に複数の事業を展開。

株式会社ユナイテッドアローズ 情報システム部 部長 兼 自社 EC 開発室 室長
大卒後、独立系ソフトウェアハウス NSK に入社。オープン系のプログラマからキャリアを開始し、 2 年目から SAP 導入コンサルティング( FI 、CO 、PP 領域)に従事。化成メーカー 2 社、建設業 1 社、精密機器メーカー 1 社への導入を経験。 2004 年秋に現職(情報戦略グループ配属)に転職。会計、人事給与、ワークフロー刷新から担当し、のち POS や販売管理を経て 2011 年から 2014 年の 3 年をかけて商品基幹系の刷新を実行。その後 EC を中心にデジタルマーケ側へと領域を広げ、デジタルマーケティング部の部長職に就任。現在は自社 EC 開発室、情報システム部の責任者。
もくじ
コロナ禍により来店客数は半減!? アパレル業界は今どうなっている?
―― まずは、アパレル業界の DX について、簡単に教えていただけますか。
そこで DX を進めていくにあたって、まずはお客様の接点、わかりやすい例で言えば e コマースなどと、旧来のアセットである店舗のお客様の体験の行き来を、いかにシームレスに繋ぐかということにフォーカスしています。
―― 天沼さんはどのように DX が進んでいるとお考えですか?
木下さんのおっしゃる通り、顧客接点が一番熱い部分で、お客様が求めているところでもあります。また、アパレル業界をデジタルの観点から見たときに、まだまだ解決できる問題が多く、ポテンシャルがすごく大きいと感じました。
―― ありがとうございます。一方で、現在のコロナ禍のお話も伺いたいのですが、実際、お客様の来店者数に影響があったのでしょうか?
大きな影響を受けました。ひどいときには来店者数が前年実績の半分を割ったこともありました。いまは徐々に状況は変わっていますが、それでも明らかに減っています。
その来店者数の減少に加えて、コロナ前後の違いを一番感じているお店のスタッフの意見を拾い上げると、みんな口を揃えて、「目的を持って来店されるお客様の割合が増えた」と言います。つまり、お客様は周りの状況や安全に気を遣ってお店にいらっしゃるので、お客様の多くが確実に来店の目的を絞られているのです。
そういうお客様が増えると、お店で何が起きるかというと、お客様が「お気に入り」などである程度、的を絞って来店されることは知っているのですが、全国 3000 人のお店のスタッフそれぞれが、個々のお客様がどういう情報をみて、どういう経緯をたどって、実際来店されたかまではわからないんです。
それが非常にもどかしく、冒頭に挙げた DX の話に繋がります。
―― 天沼さんはどのような影響があったのでしょうか? お店に行くことが難しくなり、逆に airCloset へのニーズが増えているのでしょうか?
木下さんのお話にもあった通り、ウィンドウショッピングが激減してしまったことはとても大きく、それに伴って洋服に出会うきっかけが減ったので、スタイリングを提案してもらい新しい洋服に出会いたいというニーズは増えています。
ただ一方で、みなさん外出をしなくなったので、そもそもファッションが以前ほど必要ではなくなったこともあり、業界全体で見ると、洋服へのニーズ自体は減っています。
サイズの定義がない! DX を阻む壁
―― 先ほど、天沼さんにはアパレル業界の DX には大きなポテンシャルがある、おっしゃられましたが、今の業界が抱える課題について伺えますか?
アパレル業界というのは企画から生産、販売まで 1 社で完結する会社がほぼ無いんですね。生産だけなら生産、企画だけ、そのほか、倉庫や物流だけという場合もあります。このため、サプライチェーンが 1 社で完結せず、しかも会社ごとに基準が分かれています。
DX を進める難しさは、この各社で持っているデータのルールが決まっていない上に、各社がバラバラにデータを持っていることです。これをどう繋げるかが、大きな課題です。
もうひとつ大事なのが、各社、社内で DX に向けた強い意志、本気度がどれくらいあるのか、です。
変革なので、一時期には非効率になるかもしれないし、絶対に確実にうまくいくというものでもない。この不確実な DX には経営も含めた強い意志が必要になるんじゃないかと思います。
強い意思が必要というのは、アパレル業界固有の部分にあるかもしれないですね。
例えば、我々がオリジナルで洋服を作る場合、企画は我々で行いますが、それを実装する工程においては、縫製をする工場が必要ですし、縫製工場には、ボタンなどの部材、副資材が必要で、そのボタンを作る能力は我々にはありません。
こういったエコシステムで成り立っているのが我々のビジネスです。
このエコシステムに関わっている会社の数は 1000 社を下りません。 DX を進めるには、こういった方々と共有できる目標を打ち立てて、デジタル化することで、それぞれがやりたいことをやりやすいようになる環境を醸成しなければなりません。
これは、一社のトップダウンでできるような話ではなく、サプライチェーン全体を通じて進めなければならず、相当工夫しないといけません。こういったエコシステム、関係者の多さがあるので、強い意思が求められるんですね。
関係者が多いことと、またデータのルールという点で、定義がないのは衝撃的でした。例えば、サイズで S / M / L と言っても、そもそも業界標準がないので、各社様が考える S / M / L なんですよね(笑)。お客様に「 S 」と言われて S を届けるだけじゃダメなことが、だんだんわかってきました。
今では各社様から S / M / L のサイズをいただいた上で、すべて我々で採寸し直し、それを社内の物差しに統一して、サイズを定義し直しています。現在はうまく対応できていますが、当時は、サイズ、決まってないのか!(笑)と衝撃を受けました。

洋服が「できるまで」から「お客様が手に取る瞬間」まで、デジタルで変えていく
―― 最後に、今後、アパレル業界の DX はこれからどうなるのか。まずは、天沼さんからお願いできますか
DX の一番大事な部分は目的であって、単純にデジタル化しようということではありません。例えば、弊社では「お客様の感動体験が第一」という目的のために、社内データサイエンスチームを社長室直下に置き、システムを内製化して自社で作っています。
内製化するのは、自社でデジタルのノウハウをちゃんと持っておくため、そしてデータ収集のためですね。データの基となる部分から、自分たちで設計する。データって、いい形で収集されていないと活用できないので、収集方法から設計することを意識しています。
―― 木下さんはいかがでしょうか。ユナイテッドアローズさんは DX 推進センターを新しく設置されていますが、今後の展望をお聞かせください。
これまでユナイテッドアローズは、お客様より先に「いいもの」の情報を集めて、足りないものがあれば企画してデリバリして、来店されるお客様一人ひとりを接客し、ニーズに合う、そして、それを上回るような付加価値を添えて販売する商売をやってきました。
ですが、現在はこれまでと違って、 SNS などを通じてお客様は知りたい情報をご自身で知ることが出来るようになりました。情報ギャップによるビジネスの優勢はなくなっているんですね。この状況にいかに対応するか、そのために、この 4 月に DX 推進センターを発足しました。
まず、今までの価値の源泉であったリアル店舗とデジタルの共存です。お客様は、お店・デジタルをまたいでお買い物をするスタイルに変わりました。
そこで DX でデジタルとお店をスムーズに繋ぎ、そしてお客様が声にしない声もしっかり理解し、先回りして提案する。デジタルを使ったお客様の期待を超える体験にフォーカスします。
そして同時に、お客様がモノを手にする瞬間までの物語、サプライサイドが我々のビジネスではすごく長い。旧態依然のやり方では、お客様の欲しいタイミングにデリバリすることはできません。サプライサイドにもデジタルを浸透させて、各工程を変えていくことにチャレンジします。
DX でサプライチェーン、バリューチェーンの両面にわたってお客様の期待を上回っていければと思います。
このあと、質疑応答にうつり、視聴者から SDGs など沢山の質問が寄せられ、お二方の回答をもって、ウェビナーは終了しました。
まとめ
EC 、 SNS などによって買い物のスタイルが変わり、さらにコロナ禍により激変したアパレル業界で、求められている DX を伺いました。
サプライチェーンが長いというお話を聞いたとき、業界にいる私の友人の話を思い出しました。その友人によると、アパレル業界では春夏シーズン向けのファッションショーや展示会はとても寒い冬に行われ、秋冬シーズン向けはとても暑い夏に行われ、そのサンプルはさらに半年前から準備するとのことでした。
これでは人気の変化や旬を予測するのは大変です。天沼さんが仰っていたように、こういった慣習などを「変革」しないと、必要な洋服を、必要な分だけ生産する、ということは難しそうですね。
また、外出を控えるようになり、ウィンドウショッピングもしなくなり、ファッションそのものの需要が減った環境で、パネリストお二人が共通して、 DX を使ってお客様への「新しい提案」に挑戦する、とお話されていたのは印象的でした。ただ便利なだけでなく「感動する」という体験を目指されているからかも知れませんね。
SEカレッジ ウェビナーは今後も旬のテーマをもとに継続して開催しています。ご参加お待ちしております!
label SEカレッジを詳しく知りたいという方はこちらから !!

IT専門の定額制研修 月額28,000円 ~/ 1社 で IT研修 制度を導入できます。
年間 670 講座をほぼ毎日開催中!!
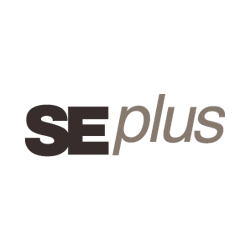
SEプラスにしかないコンテンツや、研修サービスの運営情報を発信しています。
お客様側がデジタル技術を普通に使いこなすようになり、今までのアパレルのやり方に固執してサービスを提供し続けても、お客様が受け取る価値が下がっているのが現状でした。
しかし、ここへきて、デジタルの力を使って我々自身が、お客様に最短最速で最高品質の価値を提供できる状況が生まれています。