Jリーグから学ぶサッカー業界の DX とは?|SEカレッジ ウェビナーレポート

SE カレッジでは旬のテーマをもとに、 1 時間のウェビナーを毎月 1 回以上、開催しています。
今回のテーマは、「 J リーグから学ぶサッカー業界の DX とは?」です。サッカー業界の DX は今、どれくらい進んでいるのか? サッカー業界独自の課題は何か? DX 人材に求められる少し意外な要件とは? サッカー業界の DX に携わっている 2 名のパネリストをお招きし、お話を伺いました。

株式会社栃木サッカークラブ( J リーグ「栃木SC」) 取締役マーケティング戦略部長
米国にて大学卒業後、 Microsoft 、 Google などの IT 企業勤務、起業などを経て、広告代理店在籍中に Web メディア「 kakeru 」を立ち上げ初代編集長に就任。その後同社にてスマホで写真が売れるアプリ「 Snapmart 」を企画開発。上場会社への事業譲渡後、スナップマート株式会社代表取締役に就任。 2018 年 5 月より現職。 J リーグクラブの toC 向け事業(チケット・ファンクラブ・商品化等)を統括。 X-League アドバイザーも務める。近著に「アスリートのためのソーシャルメディア活用術(共著・マイナビ出版)」がある。

アビームコンサルティング株式会社 シニアコンサルタント
法政大学社会学部を卒業後、大手 IT 企業に入社。リスティング広告の新規獲得を目的としたデジタルマーケティング、多数の大手企業のプロモーションを担ったプランナーとして活動。広告代理店に入社後は、大手自動車メーカーを担当し、ソーシャル領域における戦略設計/プロジェクトのプロデューサーとして活動。国内外の広告賞を受賞。現在はアビームコンサルティングで、スポーツ企業に向けた戦略支援(マーケティング/スポンサーシップ)に従事。
もくじ
Jリーグで進む、サッカーを「する人」「観る人」「支える人」それぞれの DX 潮流
―― そもそもサッカーにおける DX とは、どういったものなのか、酒井さんの方からご説明いただけますか
「観る人」はサッカーを愛するファンの方々のことです。
今、 J リーグではファンの見える化を行っています。 J リーグの共通基盤を通して、チケット購入者のデータや属性が見えるようになりました。こうしたファンの可視化が「観る人」の DX にあたります。
「支える人」は、例えば、ソフトバンクが 5G を導入して選手追尾映像を配信するなど新技術を導入して新たな観戦体験を推進していのが、支える人の DX です。
あとは CRM の各ツールをスポーツ界に導入して業務改善をしたり、顧客情報を管理したりという部分も進んできています。
―― 江藤さんが他に何か DX が進んでいると思うものはありますか?
コロナ禍で QR チケットはグッと進んで、ほとんどがその QR チケットを使った入場になっています。
コロナ禍で悪いことばかりですが、デジタル化が加速したという点はよかったと思います。日経新聞のニュースで「コロナ禍で DX が約 7 年ぐらい進んでいる」と報道がありましたが、私の肌感覚でも同じような印象を受けます。ここ数年、やりたいけどやれなかったことがたくさんあったのですが、それが一気にできるようになりました。
派手な DX より地味な DX が効く?
―― DX の具体的な施策については、現在どのようなことが行われているんでしょうか
「 DX = 最先端」みたいなイメージを持たれやすくて、 VR や AR といった派手な DX の話がけっこう出がちですが、私はそれだけではクラブが抱える本質的な課題は解決できないと思っています。
それよりも、例えば、チケットを買ってくれるお客様がどういった属性の方なのか、どれくらいグッズを購入しているのか。一見地味ですが、こうした顧客データの可視化ができているクラブとできてないところで、すでに売上げや集客の差も出始めています。
―― なるほど。江藤さんも同じようなお考えですか?
顧客の見える化は進んでいますね。
J リーグはいま J リーグチケットというサイトを作り、全試合のチケットが Web で購入できるようにしています。それをもとに MKDB というリーグ共通基盤となる顧客データベースを導入済みです。この仕組みが J3 のような小さな地方のクラブでも使えるようになっています。
これによって何回来場されているのか、来場が止まってしまったのは誰なのかなど把握できるようになりました。
また、そういったシステムで出力される数字に何の意味があるのかなどを分析できる知識やスキルを持っている人材がサッカークラブにはそもそも少ないため、 J リーグではデジタル人材の育成にも取り組んでいて、月 1 回、各クラブから参加できる研修を実施しています。
J リーグはこういった各クラブが利用できる共通基盤を作っていますね。
顧客の見える化で成功する名古屋グランパス
―― その「顧客の見える化」のような DX の成功事例として挙げられるようなクラブはありますか?
名古屋グランパスは一番成功しているクラブだと思います。
2015 年にデータ戦略にシフトして、まず始めたのがチケット購入者の可視化です。 2015 年当時、名古屋グランパスの J リーグチケットの利用率は 17 % 程度だったのですが、それを 2018 年には 80 % ぐらいに伸ばしました。また 2017 年に J2 に降格した際、通常 J1 から J2 に落ちると 1 ~ 2 割くらい来場者数が減る傾向にあるのですが、名古屋グランパスは顧客データの見える化がしっかりできていたので、逆に来場客数を伸ばしました。
―― 顧客の見える化で例えば、どのような施策ができるのでしょうか
例えば、 4 連勝したときに、その間、来場した女性サポーターに向けて「勝利の女神クーポン」を配布して、もう一回来てもらうというような施策を行いました。
顧客データが見えていれば、スピーディに施策もでき、それが来場につながる。愚直に PDCA をゴリゴリ回しているという印象です。
やっぱりお客様を知らないと施策は打てないですからね。逆にデータが取れないと、思い込みとイメージでお客様の行動などを判断しがちで、それを修正できないままになってしまいます。
このエリアからお客様が来てるだろうと思っていたら、違うエリアだったということもあります。それで交通広告を変えると、来場が増えたケースもあり、住所がわかるだけでも施策が変わります。
栃木 SC は少ない IT 予算でも知恵と SaaS で DX 化
DX パートナー制度で様々な SaaS を無償導入
―― それでは「サッカークラブにおける DX 化への挑戦」ということで、江藤さんから、栃木 SC での取り組みを伺えますか?
DX 化はマーケティング領域と業務の効率化のところで進めていますが、やはり IT 投資の金額は限られています。
そこで DX パートナーという、栃木SC の DX 促進をお手伝い頂く制度を設けて、色々な IT 企業に栃木 SC を通じて地元企業の皆さまに PR 頂きながら、広告料によるサポートだけでなく様々な SaaS 製品やサービスをご提供頂いています。
例えば、ベーシックさまにはその制度を通じて、 formrun という問い合わせを管理する SaaS をサプライ頂いています。
個人的にはこれが一番効果があったと考えています。
栃木SC にはシーズンパスポートやファンクラブや小さいところではスクールなどで沢山のフォームがあり、沢山の問い合わせを頂きます。今までは問い合わせを頂いていても、レスポンスが遅れたり、漏れていることもあったのですが、今は誰が問い合わせに返しているのか見える化できて、すべて返信できているだけでなく、レスポンスまでの時間も短くなりました。
これはお客様を逃さない、満足度を上げるという意味で効果がありました。ちなみに私も 1 日 30 通は返してますね。
おお、すごい。確かにレスがあるというだけでも顧客の繫ぎとめになりますね。
江藤が返しているということで驚かれることもあります(笑)。
最近では SaaS だけでなく、自社開発もしようと考えて、 RUNTEQ という IT エンジニア育成のオンラインスクールを運営するスタートアップテクノロジーさまにもその制度に参加いただき、お手伝い頂いています。
―― 予算が少ない中でも工夫してらっしゃるんですね。逆に DX で苦労したところはありますか?
toC が大変苦労していますね。いま私たちの顧客層は平均年齢 42 歳ぐらいなんですが、例えば、オンラインで申込してくださいと言っても難しい、という方がいらっしゃいます。
そこで、もっと年齢層を下げようと、この 3 年本当に色々なことをやったのですが、下がらなかったですね。また、これからも下がらないと思います。
―― それはなぜですか?
どうやっても子どもが減っているという少子化の波には抗えないんですね。
なるほど!
先日も東北のあるサッカークラブの方とお話をしたのですが、その地方では年間 1 % ずつ子どもが減っていて 10 年で換算すると 10 % 減少するんですね。なので、若年層をメインにターゲティングするよりは、 J リーグが始まった当時のファン層 40 代 50 代にもう一度来てもらう方法を探った方がよいという話になっています。
複業(副業)エキスパートを活かせ
栃木SC さんは、「複業(副業)サービスの カイコク さんともパートナー契約された」という話も話題になりましたよね。
カイコク は、デジタルマーケティング人材の複業(副業)をマッチングするサービスで、これを利用してデジタルエキスパートの方にスポットでプロジェクトに入って頂いています。
例えば、 B リーグで様々なクラブのマーケティング支援をされていた、いわばプロ中のプロの方に参加頂いていたりします。そのクラスの方の給料だと普通だったら雇えないじゃないですか(笑)。でもそういった方にスポットで入っていただいて非常に助かっています。
DX 人材候補は「器用貧乏?」
―― 最後に、もはやバズワードのようになってきましたが、いわゆる「 DX 人材」についても伺いたいと思います。 DX 人材の人材像はどうお考えですか?
求められる DX 人材の要件を見ると、あれもできて、これもできて…って、こんな神様みたいな人いるか!ってなりますけど(笑)。私は器用貧乏みたいな人がいいんじゃないかと思います。
―― 器用貧乏ですか。少し意外な回答ですね。
マネジメントもちょっとやったことがあって、現場の開発なりマーケティングもちょっとやったことある、飽き性でいろんなことやってる…みたいな人が割と視野が広くていいのかなと。いろんな問題点に気づきやすいと思うし、情報のアンテナを張っている人が多いという印象です。
―― なるほど。酒井さんはどうですか?
新しいツールを使うことのハードルが低い人っていうのがいいと思います。色々調べる前に、まず 7 日間無料だから使ってみるかってフットワーク軽く行動できる人ですね。スキルというより、もともとのベースの話ですが。
―― 意外とシンプルな特性ですね。でも確かに、世の中の変化に対応できるかっていうところでもありますよね。
では、最後に視聴者の方へのメッセージがあればお願いします!
デジタルスキルがある方がスポーツ界に来られると、もっと業界が盛り上がり売上規模も拡大できると思っているので、自分の IT スキルがクラブに活かせると思う方は複業(副業)も含めて、ぜひチャレンジいただきたいと思っています!今日はありがとうございました!!
サッカー業界はまだまだ DX の伸びしろがあるので、 IT 業界でバリバリやっていて知恵やスキルがある方なら、きっと面白い仕事ができるかと思います!
ちょうど J リーグのデジタルマーケティング職など、面白いポジションが公開されたので、ぜひサッカー業界へのご応募お待ちしています!!
このあと、質疑応答の時間となりましたが、予想以上に沢山の質問が寄せられ、今回初めて放送時間延長してお二方に解答頂くなど、好評のうちにウェビナーは終了しました。
まとめ
J リーグの DX の現場で活躍されるお二方をお迎えし、 J リーグで進む DX に加え、現場でどのような DX を進めているのかご紹介頂きました。
ウェビナー中、江藤さんは「サッカークラブと言うと大規模なイメージを持たれがちですが、 栃木SC は社員数 30 名にも満たない小さなクラブで、中小零細企業と変わらない」と何度も繰り返しお話されました。そういった規模でも知恵と工夫と「やったほうがよいと思ったら、やってしまえ」というマインドで DX 化を推進されています。
中小企業の DX 化にも通じる、沢山のヒントが詰まったウェビナーでした!
SEカレッジ ウェビナーは今後も旬のテーマをもとに継続して開催しています。ぜひご参加下さいませ!
labelYouTube でもウェビナーのダイジェスト版を公開中です
label SEカレッジを詳しく知りたいという方はこちらから !!

IT専門の定額制研修 月額28,000円 ~/ 1社 で IT研修 制度を導入できます。
年間 670 講座をほぼ毎日開催中!!
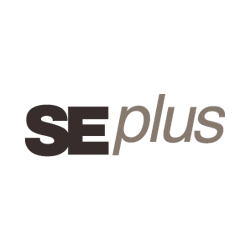
SEプラスにしかないコンテンツや、研修サービスの運営情報を発信しています。
サッカーを「する人」「観る人」「支える人」という 3 つの観点があります。
まず「する人」とは選手のことです。現在、試合時のパス本数とか、試合時のポジショニングデータなど、選手のあらゆるデータが可視化されています。そのデータは、 Wyscout というプラットフォームに格納されて、これが移籍マーケットで重要な役割を担っています。今までは、世界にスカウトマンが飛んで、実際に選手を見ていましたが、今は Wyscout を通して、特徴で選手をソートしたり、実際に選手の映像をワンタッチで見ることができるようになっています。
こういった選手データの可視化が、「する人」の DX ですね。