特集1:AI人材をとりまく市場環境と実態

AIの導入期がおわる
数年前までは「AIの導入方法とは」や「失敗しないAI開発」といったタイトルのニュースばかりが溢れていましたが、最近は様々な分野で活用されるAIの事例も目立つようになってきています。
| 年 | 検索ヒットした記事数 |
|---|---|
| 2016年 | 318 |
| 2017年 | 666 |
| 2018年 | 705 |
また、これらの事例は一部の大手企業だけの話ではなく、これまで無名に近かった中小企業が手がけ、大きな商機を手にしているケースもあります。
「AI社会実装推進調査報告書/AI白書2019(IPA刊行)」によると、
- “AIを導入している企業” は 3.1%
- “AIを導入している” 企業は “実証実験(PoC)を行っている” 企業を加えると 10.2%
です。
一方で、
- “AI導入に関心はあるがまだ特に予定がない” 企業は52.6%、
- “今後も取り組む予定はない” 企業が 10.3%
とあります。
AI 導入率の調査
調査対象
経済産業省 情報処理実態調査で調査対象となっている26業種(製造業、非製造業)の中から無作為抽出による5000事業者(内、有効回答数:350件)
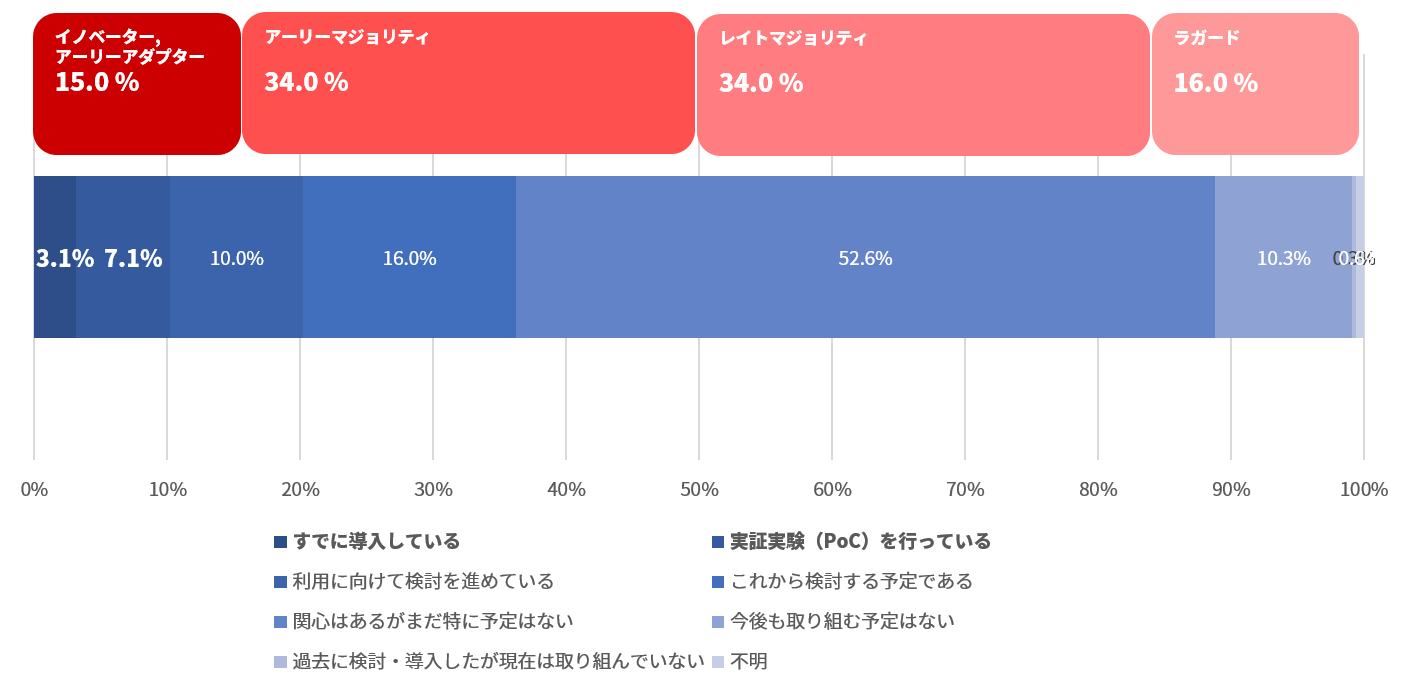
(出典: AI社会実装推進調査報告書/AI白書2019(IPA)より)
この統計から、有名なキャズム理論からすると、アーリーアダプターが反応すると言われる 15% に近づき、日本において AIは導入期は終わろうとしている ことがわかります。
また、統計だけでなくニュース記事でもその傾向がうかがえます。
たとえば、以下の、AI導入企業 (三陽商会を例にしています) のニュースを、時系列でまとめると、
AI 導入企業にみる実装の進捗
2018/10/30 AIベンダーとの業務提携のニュース
三陽商会とABEJA、業務提携に関するお知らせ|株式会社ABEJAのプレスリリース
2019/06/13 業務提携後、実店舗で実験->改善を知らせるニュース
とあり、業務提携から、わずか8ヶ月程度で、業務の改善まで進んでいることがレポートされています。
AIの普及はインターネットの普及とは比較にならないほど短期間に進むはずであり、成長期に入りつつあるのではないかと思っています。
成長期を支える「AI人材育成」は手付かず
一方で、「AIのことがまだ良くわからない」や「そろそろAIについて学ばなければ/AI人材を育成していかなければ」というスタートラインにようやく立とうとしてる企業も多いのが事実です。
先程の統計情報「AI社会実装推進調査報告書/AI白書2019(IPA)」によると、「AIを導入するにあたっての課題」の中で “AIについての理解が不足している” が 68.4% と突出 しています。
世間でこれほどAIが騒がれているにも関わらず、ビジネスになっていないのは、単にAIについての理解不足から来るものなのかもしれません。
クロノスでは「AI × Data活用研究会」という会員制の会合を定期的に開催していますが、会員企業の大半がAIについての理解をする段階であり、AIの製品やサービスに着手できている企業はほんの一握りです。
とはいえ、ゆくゆくAIもインターネットの普及と同じ状況になるのであれば、待っていてもいいだろうと構えていてはいけません。
『AIはデータが鍵 』 になります。
早くスタートを切った企業はその分、多くのデータを蓄積できますが、スタートが遅れた企業はデータの蓄積が遅れ、その分、精度の高いAIが作れず、他社に比べて商機を著しく逃しかねないのです。
今後ますますAIのビジネスは加速し、ここ2〜3年の間に今とは比べものにならないくらいAIエンジニアの需要も高まってくるでしょう。そのときには、嫌でもAIに取り組まざるを得なくなるはずです。
来るときのために、まずはAIのことを知る人材を育成するところからスタートしましょう。
label 次の特集記事

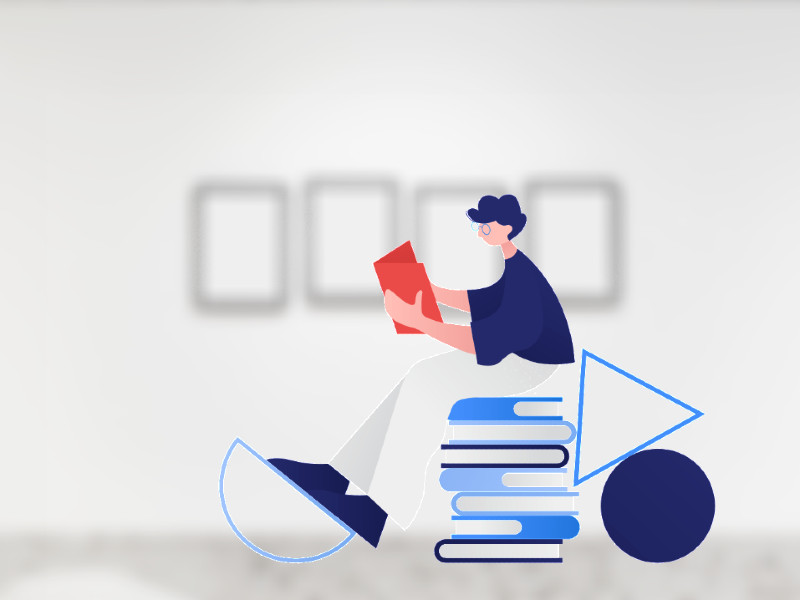

株式会社クロノス 関東事業部 ゼネラルマネージャ
「研修の受講者だけではなく、受講された方のお客様にまで、広く多くの笑顔を作る」をモットーにIT企業の技術研修やPM研修などを担当。
最近はAIの研修やセミナーにも多数登壇・講演の実績がある。
- 著作
- [記事]AI人材育成(トレタン)
- [記事]AIでシステム開発はこう変わる(AINOW)
- [書籍]Seasar2によるWebアプリケーションスーパーサンプル(SBクリエイティブ)
- [雑誌]eclipseパーフェクトマニュアル(技術評論社)
- [記事]Webの上のポジョをシームレスにつなぐJBoss Seam(@IT)
- [記事]IT人材の必要性と効果的な採用方法(@人事)
- など