特集「 IT 新人研修 をふりかえる」

もくじ
はじめに
新人研修は IT 企業の研修において、大きなウェイトを占めています。トレタン編集部の肌感覚では、新人研修の予算は、研修予算全体の 50 % は使われているように感じています。
それだけウェイトがある新人研修ですが、なかなか「大成功」と手放しの成果を収められるものはありません。
なぜ上手くいかないのでしょうか?
本特集では、その理由として新人研修にはそもそも構造として矛盾を抱えていて、その矛盾のバランスをどう取るのかがポイントであること、その上で、「講師」というバランサーの視点から「上手くいった事例」「上手くいかなかった事例」を紹介いただきます。
新人研修が成功するヒントにつながれば、幸いです。
まずは、特集記事に入る前に、事前知識として新人研修が抱える構造について、少しだけ解説します。
なお、今回の特集では「システム開発の受託企業における新人研修」を想定しています。
新人研修の構造
前回の特集で、研修コースをスモールスタート & テストを行いリリースする、というのが研修の成功には効きやすいパターンと紹介しましたが、こと新人研修にはこのパターンが使えません。
それは、新人研修には以下のような、特有の構造があるためです。
- 大規模になりがち
- ステークホルダが多い
- 新人のスキルレベルは毎年わからない
スモールスタートして、研修コースを成功する確率を高めるには「気軽に失敗する」ことが許容されていることが重要なファクタです。
ただ、新人研修は上記のような構造から失敗への許容度はとても低いため、ビッグバンリリースになり、それだけに失敗確率も高くなります。
では、なぜ、そういった構造になるのか、深堀りしてみましょう。
新人研修は大規模になりがち
以下のニュース記事より、IT 企業で新卒採用数が多い順に 10 社を抜粋した表を作成しました。
新人研修はザックリ言うと従業員数の 5 % という、結構まとまった人数が一斉に受講するイメージです。
たった上位 10 社のサンプル数なので統計的には全く意味がありませんが、参考値として出しています(読者の皆さまの肌感覚と同じでしょうか ? )。
| 企業名 | 2020 新卒採用予定数 | 従業員数 | 新人/従業員数 | 新人研修期間 |
|---|---|---|---|---|
| 富士ソフト | 650名 | 7990名 | 8% | 1~2ヶ月 |
| NTTデータ | 483名 | 11263名 | 4% | 2ヶ月 |
| 野村総合研究所 | 390名 | 6297名 | 6% | 2ヶ月 |
| NECソリューションイノベータ | 349名 | 12289名 | 3% | 不明 |
| システナ | 331名 | 2574名 | 13% | 2~4カ月 |
| TIS | 286名 | 5506名 | 5% | 2ヶ月 |
| SCSK | 279名 | 7435名 | 4% | 2ヶ月 |
| 日立システムズ | 215名 | 9823名 | 2% | 2ヶ月 |
| インテック | 180名 | 3666名 | 5% | 不明 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 163名 | 4306名 | 4% | 不明 |
| 平均値・中央値 | 5% | 2 ヶ月 | ||
- IT エンジニアだけでない職種が多い製造業などの企業は除く
- 単体の社員数が非公開の企業は除く
- 研修期間は企業のホームページより掲載
そして、これもザックリ 2 ヶ月の研修期間ともなると、
- クラス分の講師費用、教室費用の直接原価
- 研修運営に関わる人件費などの販管費
こういった費用が膨らみ、研修の中では “大規模” になってしまいます。
新人研修にはステークホルダが多い
“大規模” な研修になると、それだけ予算がかかり、経営陣の承認が必要になります。そうすると、所属部門のステークホルダだけでも 企画者 運営者 部課長 ( n 人) … 担当役員 と増えます。
また、もちろん新人の配属先の各部門からもスキル要求がありますので、現場 OJT 担当や部課長 ( n 人) … 担当役員もステークホルダになります。
それだけでなく、講師にまつわるステークホルダもいます。社内講師を立てるのあれば、社内講師の所属部門の 部課長 ( n 人) … 担当役員 と増え、社外から講師をアサインしたとしても、研修ベンダの営業、研修ベンダがアサインした講師がいます。
大規模になればなるほど、ステークホルダが増えていくことがわかります。
どこかで見たような構図ですよね。
そう、まるで 大規模な開発プロジェクト のようです。
ということは、これも大規模開発同様に、ステークホルダが増えれば増えるほど、加速度的にステークホルダ間でのコンセンサスが取りにくくなります。
大規模開発ではこれもあってアジャイルが効きにくいのですが、新人研修のカリキュラム開発もアジャイルが効きにくく、ウォーターフォールになりがちです。
例えば、開発プロジェクトで要求変更が相次ぐと、そのプロジェクトが炎上するように、研修ゴール (要求) がコロコロ変わると、研修カリキュラムもそれに応じてコロコロ変わらざるを得ず、そして、開発同様に、カリキュラムの開発工数はどんどん膨らみます。
しかも納期は伸びません。新人が入社する 4 月は死守です。
・・・ ツラくて、胃が痛くなりますね。。 😨 😨 😨
新人のスキルレベルは毎年わからない
IT 新人研修においては「プログラミング」という、覚えて終わりな「知識」だけではない、「習熟」が必要なスキルが研修成果を左右します。
読者の皆さまの所属企業では、事前にこのプログラミングスキルを測るようなものを実施されていますでしょうか ?
採用試験はもとより、内定承諾後でも未実施の企業が大半だと思います。また、システム開発の受託企業では、未経験採用を謳うことが多く、そもそもプログラミングスキルを問うていません。
そうすると、いくら基本情報技術者試験などで知識のテストをしたとしても、プログラミングができるかどうかは分かりません。そして、基準がない以上、毎年の採用次第でレベルはコロコロ変わるでしょう。
残念ながら、研修前のスキルレベル ( = プログラミングスキル ) は毎年不明です。
不明、つまり不確実性が高い開発では、アジャイルに進めることが推奨されますが、それと同様に、研修カリキュラムも、教室の現場でアジャイルに組み直しながら、実施する必要があります。
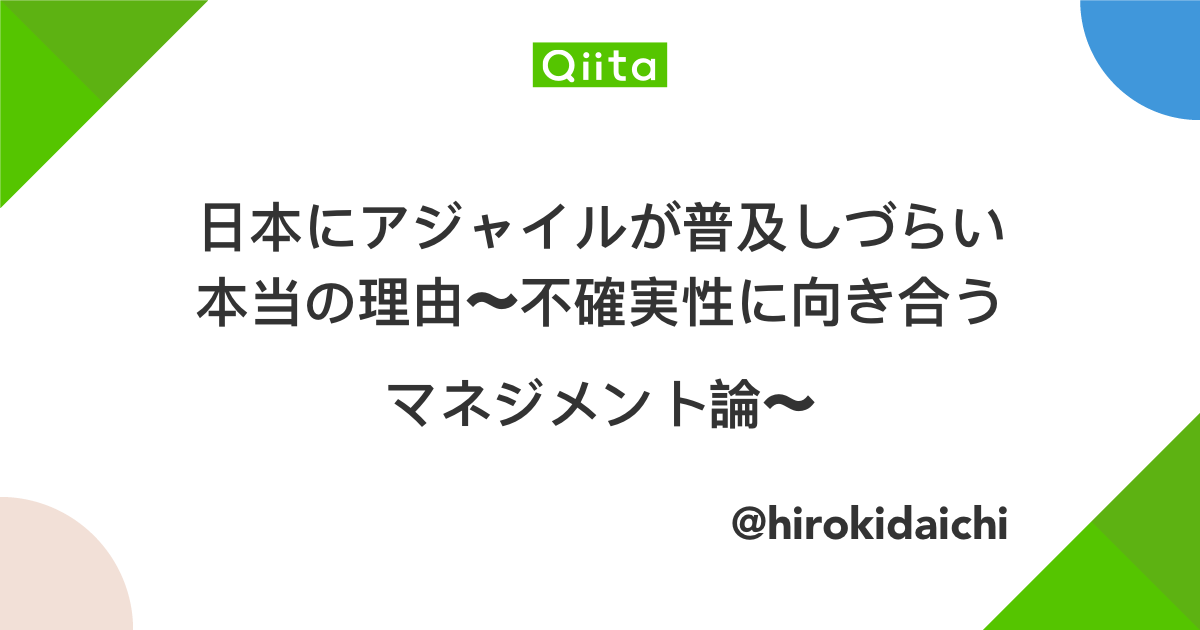
例えば、予備校や個別指導塾などでは、この不確実性に向き合うため、前提知識と合格目標に合わせてクラスを小規模に分け、カリキュラムをアダプティブに、つまりアジャイルしやすくしています。
新人研修の構造から見る矛盾
まとめとして、新人研修の構造を整理してみます。
- 研修カリキュラム開発はウォーターフォールが望まれる
- 研修現場ではアジャイルが望まれる
矛盾した構造を抱えていることがわかりますね。そして、とっても難問です。
加えて、構造である以上、どちらが良い悪いなどのレベルではなく、自然に矛盾が起こってしまいます(恐らく大規模開発でも同じようになっているのでしょう)。
これに対処するには、矛と盾をバランスさせるほか、ありません。
この特集では、そもそも失敗する構造を抱えている新人研修で、上手くいった事例、上手くいかなかった事例を紹介し、上手くいくコツを探ります。
プレゼンタは、研修ゴールとカリキュラムと、新人のスキルレベルやモチベーションと、両方のバランスを取りながら、教室の現場を司る 講師 です。
そして、いずれも講師経験が長く、かつ人気著者が多い、矢沢 久雄さん、米山 学さんのお二方を本特集にアサインしました!
この特集が、社内トレーニングに携わる、すべてのトレタンの新人研修のカリキュラム開発や、教室の現場マネジメントのヒントになることを願っています。
特集記事 目次

上手くいった IT 新人研修 、上手くいなかった IT 新人研修(1)

上手くいった IT 新人研修(2)未経験でもモダンITを1ヶ月で使いこなす

上手くいかなかった IT 新人研修(3)上手くいかないアンチパターン
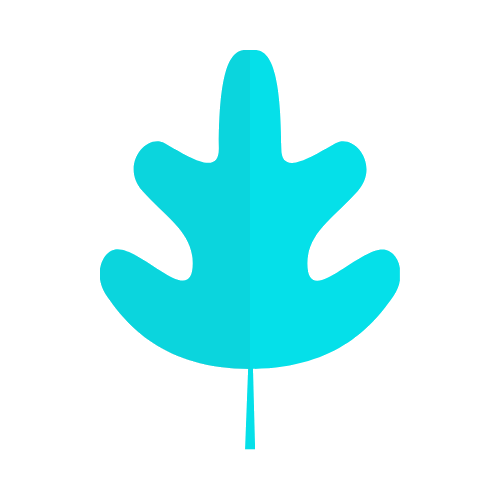
教育研修担当 (トレーニング担当者) のためのWebマガジンを編集しています。
-
- 「こんな特集、記事を読んでみたい」というリクエスト
- 「こんな記事を書いてみたい」という執筆者の方のお問い合わせ
や誤植のご連絡など、お問い合わせフォームより受付しています。
お気軽に問い合わせくださいませ!!