IT研修制度インタビュー | 株式会社アウルキャンプ ~研修制度はITエンジニアにとって福利厚生~
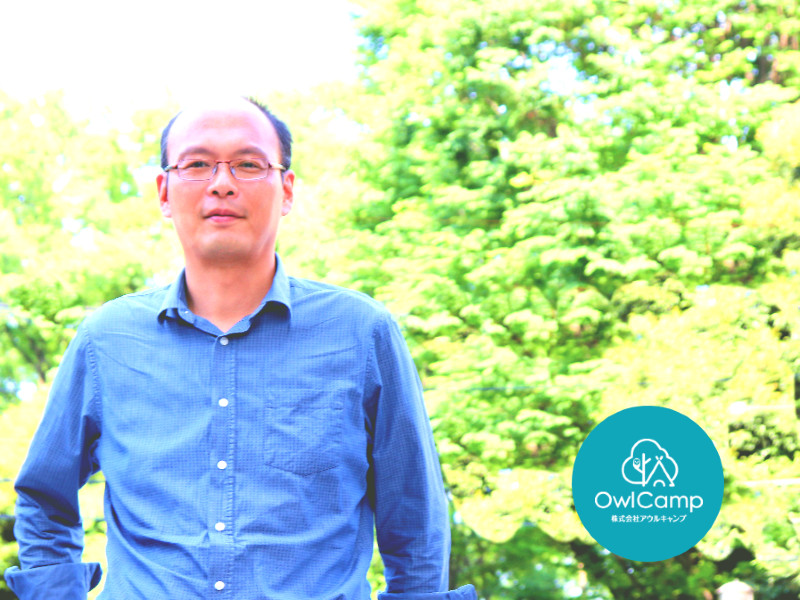
IT研修制度は、よくあるヒューマンスキルや階層別研修とは異なり、情報技術 (IT) を専門にするので、なかなか構築が難しく、また移り変わりも速いため、運用も難しいものです。
そこで、IT研修制度がどのようなものか、実際に企業様にお邪魔してインタビューして、そのコツなどを伺っています。
第4弾の企業様は、株式会社アウルキャンプ さまです。
今回は制度設計/構築された 永野さん にインタビューさせていただきました!

永野 啓史 さん
数年前までは開発現場にもたち、PHPなどで開発。現在は CTO 派遣 や DevOps などの新サービスを管轄
もくじ
現場では「5分」の Tips 教育が限界
いまの開発現場で起こっていること
-研修制度を、今年 (2019年) から導入されたとのことで、どのような背景があったのでしょうか?
そもそも、当社はお客様先でITエンジニアが開発サービスを提供する、いわゆる SES を行っています。
その中で、新人向けの研修コースはいろいろ選択肢が増え、充実しているのですが、それが終わったら、そのあと、受講できるものが何もなく、 SES では「入社して、お客様先に出たまま」という状態になりがちです。
また、開発現場に入ってしまうと、「特定のプロジェクトに特化した技術やお客さんのローカルルールを覚えてね!」という現象が少ならからず存在し、そのプロジェクトでは大活躍できるのですが、新しい技術や情報を入手しずらいという問題がありました。
そこで、これはいかんということで、早急に研修制度を作ろう、となったんです。
また、その研修で受講するコースは、「現場の技術や、その延長線にある技術ではなくても構わない」 としました。
-いまの現場で自分の知識・技術が足りないから、研修を受講することが多いと思うんですが、それは問わない、ということでしょうか
そうですね。
例えば、 Java を扱う現場に入ったとして、 Java だけ知っていればよい、という時代ではなくて、使用しているIDEや開発環境、例えば、今のモダンな現場であれば Docker を使って開発環境を作って、そのまま Kubernetes にデプロイするなど、本当にたくさんの技術が取り巻いています。
技術を1つ2つ学んで、現場で求められるスキルのギャップを埋める最初の課題はクリアできても、それ以外の知識や技術が現場毎に異なったりするので、社内で研修を実施するには、それを教えるスキルとか教える時間や工数が見合わず、とてもカバーしにくい状態でした。
また、一方で、イマドキの開発現場では、その1つ2つだけの知識・技術だけでは通用しなくなっているんです。
「5分」の実態と、これからの技術の身につけ方
-なるほど。もう Java できます! Oracle できます! Cisco できます! では、厳しいんですね
はい、Java の開発プロジェクトに参画した時に、例えばソースコードの管理は、この現場では昔ながらのフォルダに上げて管理、あっちの現場では Git を使った管理など、もうお作法はバラバラです。それらの現場のお作法に合わせて、まとまった時間をとって教えることは出来ないんです。
なぜかというと、現場にいるITエンジニアが教えられる時間は 「5分」 だからです。
-5分 ですか?
「これ、こうやると出来るから。なんか動かなかったら聞いてね」、このやりとりで 5分 です。
このやりとりが、動かなかったり、質問のたびに、繰り返されるだけなんですね。
もちろん、場合によって、課題を与えて、調べながら進めてね、ということはあるのですが、それでも Tips のような断片を端折りながら先輩が伝え、教えるだけなので、体系的に教えることが非常に難しいのです。
なので、現場では、知識やスキルを順序よく段階を踏みながら、かつ、バランスよく広げながら、身につけることが難しいんですね。
そのときに必要になるのが、業務で携わるもの以外の “新しいものへの興味” だと思っているんです。
例えば、JavaScript を学ぶと、サーバサイドでも JavaScript が書けることを知り、 Node.js を学び、そうすると Express (注) に繋がり、 API サーバを作る、というように、どんどんマッシュアップするような感覚で、技術が混ざりながら、新しくなっているので、「繋げながら学ぶ」ことが必要になっています。
そんな時代なので、学ぶものを「指示待ち」するのでは遅く、自分の興味をもとに、どんどん学ぶことが重要 になってくるんですね。
Express
Node.js の代表的なWebアプリケーションフレームワーク
永野さんが考える 「ITエンジニアの本質」
ITエンジニアがやりたいこと
-「新しいものへの興味が必要」というのは、永野さんのご経験からも、そうお感じになるのですか?
そうですね。それもありますし、そもそもITエンジニアになった人は、「知らないことを知りたい」 ために、このIT業界に入ってきたと思っているんですね。
やっぱり、新しいガジェットが出てくれば、手にとってみたいし、そういった新しいものを追いたいがために、この業界に入っていると思うので、知らないことを知れる機会はとても重要だと思っています。
-たしかに、ITエンジニア、ガジェット大好きですね (笑)
はい。(笑) また、もう一つの側面として、現場の開発業務を画期的に上手くやるようなアイデアは、その中の業務からは出てこないと思っているんです。もちろん、ロジックを見直して、業務の進め方が少し改善されることがあっても、劇的には変わりません。
-というと、具体的にはどんなものでしょうか?
例えば、Java で Eclipse を使っていたとして、それだけでは IntelliJ IDEA のような開発者が楽しく、効率的になるようなツールは知れませんし、例えば、FTPでデプロイしているような現場で、それしか知らなければ、GitHub などを使ったデプロイを知ることはありません。
また、「現場で解決出来ない」という問題があったとして、「今の環境・技術だから出来ない」のか、「技術的に不可能」なのか、それには、現場外の知識や研修で知らないことには判断ができません。
-たしかに、その現場だけに閉じた知識や技術では、それは出来ないですね
私自身は、ITエンジニアは、知れば知るほど、良質なアウトプットができる と思っています。
「知らない」と「知っている」では、「0」と「1」ぐらい差があって、知らなければ 0 のまま、いつまでも出来ません。
ですが、色々な課題に対して、色々な 1 があれば解決できる可能性があり、知識と知識がつながって別のものになることもあります。
ITエンジニアはナレッジワーカーと言われるのも、このあたりにあると思います。
-なので、知らないことを知ってほしい、と
はい。また自分のキャリアを考える上でも、現場に閉じたものではなく、他の土台があったほうが自由度があります。
技術と同じだけ「人」としてのスキルが必要
-だから、SEカレッジではアウルキャンプさんのメインのインフラ系技術 「ではない」 コースを受講されているんですね (補足: 導入6ヶ月で、のべ77名が受講)
それもそうなんですが、それはまた別の理由なんです。
当社には25名のITエンジニアがいるのですが、主軸となっていたインフラ系のエンジニアは、もう4割ぐらいになっているんですね。一方で、当社で始めた DevOps のような新しいサービスで、従来のインフラより、もう一段高いレイヤーの仕事がしたいと考えています。
その育成には、従来のインフラ系エンジニアから育成するより、開発系のエンジニアからシフトさせたほうが早いと考えているので、インフラではなく、開発系やヒューマンスキルのコースを受講しているんですね。
-なるほど、確かに Development(開発) と Operations(運用) 、 Infrastructure as Code というぐらいですから、コードを書くことに慣れている開発系エンジニアのほうが早いかも知れませんね
またもう一つあった、ヒューマンスキルのコースを受講している背景には、当社の場合、お客様先で開発をするので、技術だけでなく、「人」としても信頼されなければいけません。
なので、 「技術スキル」と「人としてのスキル」が同じ割合だけ必要 なんですね。
人としてのスキルが高くても、技術スキルがなければ信頼されませんし、技術スキルが高くても、人としてのスキルがなければ、これもまた信頼されません。
そういった考えで、当社の研修制度では「人としてのスキル」も上げることを謳っています。
-では、その研修制度では、どのようなスキルを身につけるように設計されているのですか?
入社後だいたい3年で、業務に慣れて、技術スキルとしても「詳細設計」ぐらいまで任されるようになりましょう、と。現場ではサブリーダークラスですね。
それ以上のレイヤーとなる、「基本設計」以上を任されるようになるには、技術だけでなく、お客様と信頼関係を築き、チームで仕事ができなければなりません。
これをザックリとした人材モデルにしています。
この人材モデルを社内では展開していて、それをもとに、「自身が興味をもった」コースを各自で受講しています。
-それ以外に、細かにスキル要件を決めていたりするのですか?
いえ、決めていません。先程の通り、ITエンジニアによって、やりたい技術やキャリアは変わりますので。
ただ、今は人数が少なく、個々のキャラクターやスキル、志向などを私が分かっているので、「こういうのはどう」「もっとこういうことをやるのはどう」という提案のメッセージを込めて、研修コースをアサインすることもあります。

IT研修制度はITエンジニアにとって「福利厚生」のようなもの
「クラウドに強い」とは、どんなスキルターゲットなのか
-永野さんの個人的な考えとしても、そういった求めるスキルのようなものはないのですか?
うーん、、個人的には、開発系もインフラ系も関係ないスキルとして、「SQL」や「Linux」のようなベーシックなものは必要ですかね。それ以外は、開発寄りになってしまったり、インフラ寄りになってしまったりするように思います。
ちなみに、開発とインフラの区分けが、実態が「開発か、それ以外」のようになっていて、個人的には区分けするような考えが好きではないんです。なので、DevOps のような世界が好きなんです。
-なるほど、それで DevOps だったんですね
当社としては、そういった DevOps の土台となる “クラウド” に強くなろう と考えています。
現在、1割ぐらいのリソースを割いて、社内のWebやシステム、Android アプリなどを開発していて、そのバックエンドは AWS を使っています。
-クラウドですか。それはまた、なぜ、そのようなお考えに?
クラウドの市場が広がっているのが一つですが、一方で、こういった SES のような会社で「クラウドに強いですよ、とても得意ですよ」と言っている会社が少ないんですね。一方で、「技術力は高いですよ」とは言っていたりします。
であれば、当社はしっかりと、ターゲットの技術を明確にして “クラウド” としました。
それとあわせて、社内の研修制度には資格手当があるのですが、その中に AWS 資格 を入れて、絶賛推奨中です。
実際、AWS ソリューションアーキテクト アソシエイト の資格を取得したITエンジニアが AWS を扱う案件に入っています。
-ただ、クラウドになると、今までのようなインフラ構築、運用のような売上が期待しにくいと思うんですが
たしかに、インフラとしての構築・ランニングの売上は下がりますが、保守開発というアプリケーション開発の売上は変わりません。
-なるほど! 確かに、開発の売上は下がりませんね
そういったクラウドでの開発だからこそ、従来の開発・インフラではなく、今までの技術の土台の上に、これまでになかった知識・技術も必要になります。
例えば、チューニングと言っても、今までは開発 / インフラで分かれて行っていましたが、いまはもう一緒に考えないと出来ません。つまり、クラウドでは技術が地続きになっています。
-となると、領域が広く、ターゲットスキルの設定が難しいですね
難しいのですが、RDS や EC2, S3 のような 単なるインフラの載せ替えではないことが出来るようになる、 ということをターゲットにしています。
例えば、AWS Lambda を使ったサーバレスや、ビッグデータ収集基盤の構築から管理、AWS Cognito を使った認証管理など、 “クラウドならではの技術ができる” ということまで到達できれば、強いと考えています。
-なるほど、それはとてもわかりやすい目標ですね。
一方で、クラウドで悩ましいのが Amazon (AWS), Google (GCP), Microsoft (Azure) のどれにするか、というところですが
当社は AWS です。やはり、ドキュメントが充実しているので、入りやすいですね。
GCP も触ってみたのですが、サービス面で、やっぱり AWS に無いものが多いように感じました。 流行りの Firebase(注) を試してみたところ、まだまだ詰まるところが多かったです。また、これはこれで挑戦してみたいですね。
Firebase
Googleが買収・開発した NoSQLのDBMSが核になったサービス。バックエンドに注力せずとも開発できる (MBaaS) というコンセプトを持つ。
やはり、現在のお客様の要望として、オンプレミス -> クラウド移行 にあるので、対応するサービスが少ないと、移行がすんなりできず、どうしても再設計する必要が出てきてしまいます。
このため、AWS が良いと考えています。
もちろん AWS のシェアも大きいですしね。
-ちなみに、”研修制度はあくまで興味重視” というところで、強制力が無いまま、クラウドへのシフトはどのようにやろうとお考えですか?
そこは、やはり各エンジニアの「選択」になります。
やりたい人が集まって、いつか「部門」、例えば、クラウド開発部のようなものを立ち上げていこうと考えています。器が無いことには集めにくいので。
-それも「やりたい」志向なのですね。(笑)
ITエンジニアにとって研修制度は、報酬の一種である「福利厚生」
-これまで伺っていると、やはり、アウルキャンプさんの中の人は「~をやりたい!!」のような Want が無いと厳しそうですね
やっぱり、「これやりたい、あれやりたい」など良い意味でモノを言う人がいますし、当社としても、その方がありがたいですし、歓迎しています。
というのも、個人的には、会社を自動車に例えると、会社はハンドルであって、エンジンは「本人」なので、いくらハンドルを切っても、エンジンが動かないことには前には進まないと思うんですね。
もちろん「エンジン」なので、「ゆっくり」や「速い」も本人のペース次第ではあるのですが、あくまでも、ITエンジニアの「やりたい」がエンジンです。
その「やりたい」のガソリンのようなものが研修制度で、 研修制度は、ITエンジニアにとっての金銭だけではない報酬、つまり福利厚生である と考えています。
-研修制度が一種の報酬であるとは、位置づけがとてもユニークで、わかりやすいですね
それだけでなく、当社の場合、有給休暇とは別に 「研修休暇」 というのを用意していて、それが 年間 5日間 あります。なので、みんな、それを使って参加しています。
まさしく、研修制度が “福利厚生” になっていますね。
アウルキャンプさんは GitHub で 就業規則を公開 していることでも話題になりましたが、研修休暇も、その就業規約に載っています。
-とても素敵な制度運営ですね。
では、その研修制度として、SEカレッジをご導入頂いたのには、どのような理由があったのでしょうか?
さきの話の通り、ヒューマンスキルのコースだけではダメですし、技術的なコースだけでもダメで、そのどっちもがある、ということが評価ポイントでした。
あわせて、現在、積極的に若手層の採用を進めていて、毎年10名ぐらいのペースで入社しています。その “若手層の育成” ということも課題に挙がっていたので、導入しました。
ちなみに、今年は15名の採用目標で活動を進めています。
-このITエンジニア採用難の時代に 毎年 “10名” 採用はスゴい。。
ITやりたいけど、「まだ機会がない」という人口は多く、当社はその層をターゲットにしています。
また、採用ターゲットというだけでなく、社のミッションとして、 “情報技術で社会貢献できる人を増やす” ということを掲げているので、それもあって、とにかく「やってみたい」という人に入ってもらっています。
そして、入ってもらったからには研修制度を通じて、育成しようと考えています。
-なるほど! そういった背景があったのですね。
では、最後に何かメッセージがあれば、お願いします!!
「ITエンジニアになりたい」でも「IT業界でキャリアアップしたい」でも、とにかくチャレンジしたいという気持ちがあれば、未経験でも大歓迎です。
じっくりとキャリアパスなどについてお話ししながら、スキルレベルに合うプロジェクトに参加してもらいますので心配はいりません。
誰でも最初は経験がありません。DevOps や AWS を知らなくても大丈夫です。
必要なことは、入社後に身に付けていってもらえればいいです。
諦めずにチャレンジする気持ちさえあれば、それを全力でバックアップします。

-では、今日はありがとうございました!!!
ありがとうございました。

IT専門の定額制研修月額25,000円 ~/ 1社 でITの研修制度を導入できます。
年間500講座をほぼ毎日開催中!!
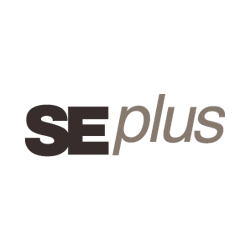
SEプラスにしかないコンテンツや、研修サービスの運営情報を発信しています。
